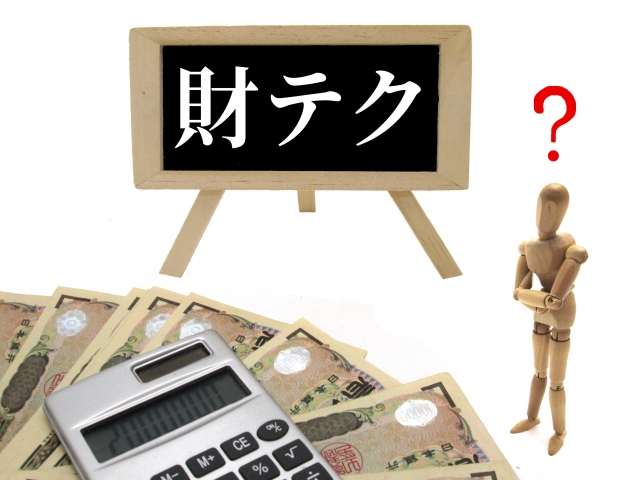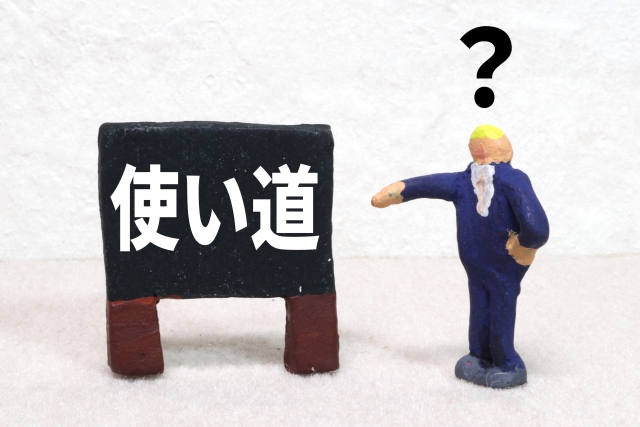手形を取引で利用するタイミングはいつ?様々な疑問をわかりやすく解説!

約束手形や為替手形などは有価証券として扱われていますが、近年では使われることが少なくなったため、ビジネスにおいてどのタイミングでどのような場合に使えばよいのか分からないという方もいることでしょう。
そこで、取引に手形が用いられる理由や、どのような取引において使われるのかをわかりやすく解説します。
そもそも手形とは何?
手形は古くには一定の内容を証明する証文に押されていたことから、その後、資格や権利を証明する書面自体を指す言葉として使われるようになりました。
商取引において用いられる手形として、約束手形や為替手形などが挙げられますが、これらは商品やサービスを購入するにあたり、その代金を一定期間過ぎた後で支払うことを約束するための有価証券です。
手形を用いるタイミング
日本では掛けによる商取引が一般的ですが、掛け取引では商品やサービスを購入後、その代金に対する請求書が発行され、期日までに入金されることになります。
手形を用いた取引では、商品やサービスを購入後、現金で支払う代わりに手形を振り出します。
手形を受け取って代金を受け取るまでの流れ
手形の支払期日に受取人である販売先が取引銀行に手形を呈示すると、受取人と振出人、それぞれの取引銀行が手形交換所で手形を交換することになります。
その後、振出人の取引銀行の当座預金口座から、受取人の取引銀行へその金額が送金されて、受取人は現金を受け取ることができるという流れです。
【呈示は忘れず行うこと!】
ここで重要なのは、受取人が取引銀行に対して手形に記載されている期日を含め、銀行の3営業日以内に手形を呈示する手続きが必要ということです。この呈示が行われない場合、口座に手形の支払いが行われず、代金を回収できません。
なお、呈示を忘れていて入金されない!というトラブルが発生してしまった場合、支払いに充てる資金を調達しなければならなくなります。このような場合、売掛金を保有しているなら期日より前倒しで現金化できるファクタリングを利用しましょう。
ファクタリングを利用する場合には手数料が発生しますが、業者によって大きく異なります。そのため事前に見積もりを取得した上でどの業者に売掛金を買い取ってもらうか決めることが大切ですが、ファクタリング専門業者は大変数多く存在するため、一社ずつ見積もりを請求するのはかなりの手間がかかってしまうかもしれません。
ただ、複数社から一括で見積もりを取得できるアイミツサイトなどを活用すれば、ファクタリング専門業者を選びや資金調達がスムーズに運びます。
なぜ商取引に手形が使われるのか

普段の取引に手形を使うことがない企業も多いでしょうが、建設業界などでは用いられることが多いようです。
ではなぜ、わざわざ手形で支払いをする必要があるのかというと、次のような理由があります。
理由①下請法より支払いを遅らせたいから
手形が用いられる理由は、下請代金支払遅延等防止法より支払いを遅らせたいからです。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)とは、下請事業者の利益を保護するための法律です。この法律では、下請事業者からの請求の有無に関係なく、物品などの受領日から起算して60日以内に定めた支払期日までに、下請代金はすべて支払わなければならないとされています。
60日以内ということは、末締めの場合には翌々末には支払うことが必要となりますが、下請法を遵守する必要のある対象事業者は多くが大企業ですので、支払う金額も大きいことが特徴です。
そのため、60日以内では負担が大きすぎるのでできる限り後ろに遅らせたいと考えてしまうのでしょう。このような場合において、下請法に触れることのない手形を振り出し、支払期日を遅らせることに利用されています。
理由②掛けによる取引よりも確実に支払われる可能性が高いから
掛けによる取引では代金に対する請求書を発行すると、後は期日に入金されるのを待つことになります。ただ、取引先がうっかり期日を忘れていたり、経済的な事情などで支払われなかったという場合も出てくるかもしれません。
支払いが行われなかった場合には、未入金となっている事実を取引先に伝え、いつまでに入金してもらえるのか確認することが必要です。場合によっては、訴訟などの手続きが必要となることもあるでしょう。
本来の期日に入金があるはずだから…と、仕入代金や経費、給料などの支払いを予定していた場合、何らかの方法で資金調達も必要となります。
しかし、手形を用いた取引であれば、手形の振出人は期日に遅れることなく代金が口座に入金される確率は高まります。
【手形のほうが掛け取引より確実な理由】
手形の場合、支払期日を過ぎても手形額面の金額が相手に引き渡されないと、不渡りという扱いになります。
この不渡りを出してしまうとすべての金融機関に通知が届くことになりますが、仮に6か月以内に2度不渡りを出してしまうと、銀行取引停止の処分対象です。
銀行取引停止処分の対象になれば、2年間、金融機関での当座預金取引や融資を受けることはできなくなります。これは事実上の営業停止扱いとなり、倒産とみなされることになるため、不渡りを出さないよう確実に期日が守られる可能性が高いということです。
理由③手形取引は当座預金を開設できる法人だけの特権だから
手形取引は当座預金口座がなければ利用できませんが、法人名義の当座預金口座は経営状況が良好であり、十分に銀行との取引実績がなければ開設できません。
そのため手形を利用できるということは、社会的に信用力の高い法人だとみなされやすくなります。
手形の支払期日は誰が決める?
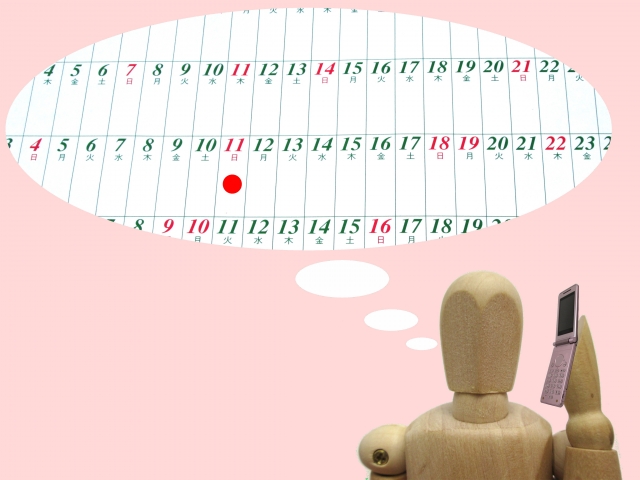
手形の額面金額がいつ支払われることになるのか、その支払期日を決めるのは振出人と受取人です。
双方が合意の上で決定されることになりますが、振出日から支払期日までを手形サイトといいます。
一般的な手形サイトは、30日、60日、90日、120日なおですが、中には1年という長期に渡る手形が取引に用いられることもあります。
手形サイトは双方が合意の上で決める期間ですので、支払期日までの期間が長すぎると、その間に振出人企業が倒産してしまったり、代金回収までの期間の資金繰りが悪化するリスクを負うことになると理解しておくべきでしょう。
もし手形の支払いサイトが長めに設定されていることで、支払いに充てる資金が不足した場合はファクタリングによる資金調達を検討するとよいでしょう。
ただ、ファクタリングを利用する場合は業者選びが重要です。複数社から一括見積もりが可能なアイミツサイトなどを活用し、円滑に資金調達を行うことをおすすめします。
約束手形と為替手形は何が違う?
約束手形はこれまで説明した通り、振出人と受取人の2者で支払期日を決め、その期日に代金を支払うことを約束するための有価証券です。
これに対し為替手形は、振出人と受取人以外に、支払人が取引に加わります。
たとえば、
- 振出人…B社に買掛金、C社に売掛金があるA社
- 受取人…A社に売掛金のあるB社
- 支払人…A社に買掛金のあるC社
とします。
A社はC社に対し、B社に対する買掛金を自社に代わり支払うよう、為替手形の引き受けを依頼します。
C社が承諾した後、A社はB社に対して、自社の買掛金はC社が代わりに支払うことになったので、C社から受け取るように為替手形を振り出します。
B社は買掛金の支払いとして、A社から振り出された為替手形を受け取り、支払期日になるとC社からB社にA社の買掛代金が支払われるという流れです。
B社とC社は直接関係ありませんが、それぞれが為替手形の振出人であるA社と売掛金や買掛金の関係がある場合に、効率的に対応するために用いられることが多いといえます。
ただ日本の商取引においては為替手形はあまり利用されることがなく、約束手形が用いられることが多いようです。
まとめ
手形とは、商品やサービスの代金を支払う際、一定期間後に支払うことを約束するために発行される有価証券です。
大企業が下請企業などに対しを発行されることが多いのは約束手形で、一定期間支払いを遅らせることができる部分がメリットといえるでしょう。
ただ手形を受け取ることになる企業にとっては、支払期日までの期間の支払いに充てる資金が不足する可能性もありますので、その場合には売掛金を現金化するファクタリングなどで資金調達することも検討するようにしてください。
なお、ファクタリングは業者選びが重要です。どの業者に依頼するか決める場合、見積もりを取得して手数料やサービス内容などを比較・検討することになるでしょうが、一社ずつ見積もりを取得するのは手間がかかります。
手間や時間をかけずに複数のファクタリング業者から見積もりを取得したい!という場合は、複数社から一括で見積もり取得が可能なアイミツサイトを活用することをおすすめします。