日本だけでなく世界の経済が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていますが、その影響は製造業を営む中小企業などにも及んでいます。
ほとんどの国で市場の正常化に時間がかかると考えられていますが、日本の企業のほとんどは中小企業であり、製造業などは早期に回復した中国などに影響しやすいことが特徴です。
世界的にはすべての産業で新型コロナによる景気後退の影響があり、特に自動車・航空宇宙・繊維産業などはロックダウンや売上不振の打撃を受けています。
資金不足で事業継続を危ぶまれる製造業を営む中小企業も少なくない状態ですが、今後回復の見込みはあるのでしょうか。
目次
そもそも製造業における中小企業とは?
「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に基づいた「中小企業者」のことであり、製造業における中小企業とは次のいずれかを満たす企業です。
- ・資本金が3億円以下
- ・常時雇用する従業員が300人以下
ただし、ゴム製品製造業は資本金3億円以下、または常時雇用する従業員数900人以下であることが要件となります。
常時雇用する従業員数が20人以下の場合には、中小企業者ではなく小規模企業者に区分されます。
この中小企業の定義は中小企業政策での基本的な原則であり、法律や制度などにより中小企業として扱われる範囲が異なることがあります。
新型コロナで影響を受けた中小企業の現状は?
日本経済の実質GDP成長率の推移のうち、2019年の年間成長率は0.7%で2018年を上回っていました。
しかし公需が経済を下支えする中、消費税率が8%から10%に引上げされたことに伴った駆け込み需要の反動減に加え、台風や暖冬などが影響して第4四半期は5四半期ぶりのマイナスになっています。
中小企業・小規模事業者の業績は、2019年以降は横ばいから低下傾向で推移し、業種別でみればオリンピック開催に伴って需要が拡大した建設業を以外は低下傾向での推移がみられました。
製造業への影響は?
日本ではどの産業でも少子高齢化による生産年齢人口減少の影響を受け、人手不足が深刻化しています。中小企業でも人手不足の影響を受けていますが、新型コロナによる影響を業種別に見ると、サービス業やその他の業種で売上機会の逸失を感じている割合は高くなっています。
それに対し製造業では、新型コロナによる残業時間が増大していることや、納期遅れのトラブルなどが問題になっているようです。
2019年は台風など自然災害が立て続けに発生し、様々な中小企業に影響をもたらすことになりました。
自然災害に対する経営上のリスクに、十分に対応を進めているとするケース、またはある程度対応を進めているといえるのは大企業が全体の4割で中小企業は2割程度です。
中小企業は大企業よりも自然災害のリスク対応が進んでいませんが、半数以上が大企業・中小企業に関係なく進んでいない状況といえます。
自然災害ではないものの、リスクが影響することになった新型コロナの発生で、企業活動には大きな影響が及んでいます。
実際、政府系金融機関や商工団体などに設置された新型コロナウイルスに関する経営相談窓口での相談のほとんどは資金繰り関連であり、飲食業・製造業・卸売業・小売業・宿泊業からの相談が多いようです。
中国の生産・貿易減少で影響が及ぶ生産活動
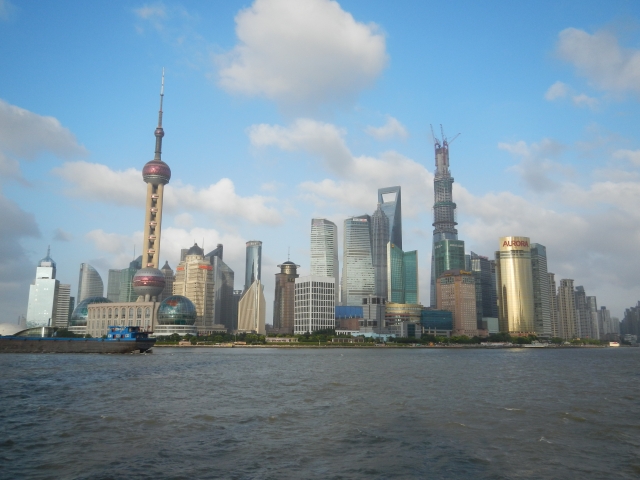
新型コロナが拡大したことで中国の生産・貿易も減少し、中国に関係のある日本の中小企業にも大きな影響が及ぶことになりました。
中国に海外子会社がある中小企業を業種別に見ると、卸売業・その他の製造業・生産用機械・輸送機械・化学・金属製品などが多くなっています。
さらに仕入れを中国に依存している傾向が高い業種を見ると、電気機械器具製造業・電子部品/デバイス/電子回路製造業・生産用機械器具製造業・情報通信機械器具製造業など製造業ばかりです。
製造業は中国から輸入が減少してしまえば、たちまち生産活動に影響が及ぶことが確認できることでしょう。
新型コロナにより、2020年2月は中国からの部品が調達できず、生産活動が停滞するといった影響もありました。
今後は日本の主要な輸出先の欧米で新型コロナ感染が拡大していることから、輸出が減少するといった影響が大きくなることが予想されます。
国内消費が減少してしまったことで業況が悪化に
新型コロナが影響したことで国内消費も大幅に減少することになりました。
外出自粛などの影響により買いだめなどが発生したことで、小売業は一部売上増加もあったでしょうが、全体で見れば業況は悪化しています。
製造業の場合、新型コロナの感染拡大が始まった2020年1~3月期は、パルプ・紙・紙加工品で大きな低下が見られるなど影響が及ぶこととなりました。
特に2020年2月以降は大幅に景況感が悪化し、先行きの見通しも悪い状況で雇用への影響も懸念されます。
製造業は一時期よりは持ち直したとはいえますが、それでもいまだに多くの製造業が苦しい状況にあるといえます。
2021年は製造業を営む中小企業にとってどんな年に?
2021年も新型コロナによる影響は避けらず、ワクチンなどの効果が期待されますがまだ先行きは見通しが立ちません。
2020年3~5月にはほとんどの企業で緊急対応が必要でしたが、現在は通常業務に新型コロナによる状況を組み込みながら対応する準備が整いつつある状況です。
柔軟な対応と持続できる仕組みが、今後の企業の体制やシステムに必要になっていくでしょう。
製造業での新型コロナの影響として挙げられることの1つが供給面の問題で、ロックダウンなどが影響し人やモノの移動が制限される中、サプライチェーンの分断や生産停止という状況が生まれたことです。
設計面・部品調達の他、人員を送ることができず製造品質を保つことができなくなり、予定通りのモノを作ることができない状況が続いています。
さらに医療関連機器やマスクなどの需要は高まる一方、人の移動が制限されたことが影響し需要が急減した製品分野も出てきています。
そこで製造業では、リモートワークなどを組み合わせながら対応する企業も増え、いつ収束するかわからない新型コロナの動向に左右され続けることに不安を抱えているようです。
今後、製造業が行っていくべきことは?

製造業では今後、持続性のある業務プロセスを考えていかなければなりません。
モノを扱う以上は現地・現物・現実の価値を最重要とするべきですが、新型コロナで人の移動が制限されたことでより生産のデジタル化への取り組みが重視されています。
オンラインで量産立ち上げをするしかない製品なども数多く存在しているため、デジタル技術を取り込んだモノづくりのプロセスを構築させていくことが求められます。
資金が枯渇すれば元も子もなくなる
ただしやらなければならないことはわかっていても、資金面での体力が十分でない中小企業の場合、どうやって資金を調達すればよいか悩むこともあるでしょう。
国からの補助金や政府系金融機関からの融資などを利用する場合でも、今手元の資金が枯渇してしまえば事業を継続できず、次の段階に進むことはできなくなります。
すでに資金繰りが悪化している場合など、まずは改善させることから考えていかなければなりませんが、このような場合にはファクタリングを活用してはいかがでしょう。
負債を増やさず決算書を汚さず資金調達
ファクタリングとは、保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、取引先が支払う期日よりも先に現金化させるサービスのことです。
中小企業の資金調達の方法といえば、銀行から融資を受けることが真っ先に浮かんでしまうものですが、ファクタリングのように借金を増やさない方法もあります。
特に補助金や政府系金融機関から融資を受けることを予定している場合には、提出する事業計画書や決算書なども重要になるため、負債を今より増やしたくないと考えてしまうものでしょう。
一時的な資金ニーズに迅速に対応できる手法として活用できるのがファクタリングのメリットなので、検討してみることをおすすめします。
まとめ
新型コロナの影響は製造業に限らず様々な産業に及んでいますが、日本の経済を支える中小企業が特にその打撃を受けているといえます。
今対策としてできることは何か考え、将来的に実践したくても手元の資金がなくなり事業を続けることができなくなれば意味がありません。
そのためにもまずは手元の資金を確保すること、次に製造業が行っていくべきことへつなげるために資金繰りを改善させていくことを検討しましょう。
補助金や日本政策金融公庫から融資を受ける場合でも、事業計画書や決算書を提出することとなりその内容が重視されます。
また、申請した後も実際にお金を手にするまで時間もかかるため、借金を増やさず資金を調達できる方法を選び活用することをおすすめします。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。





