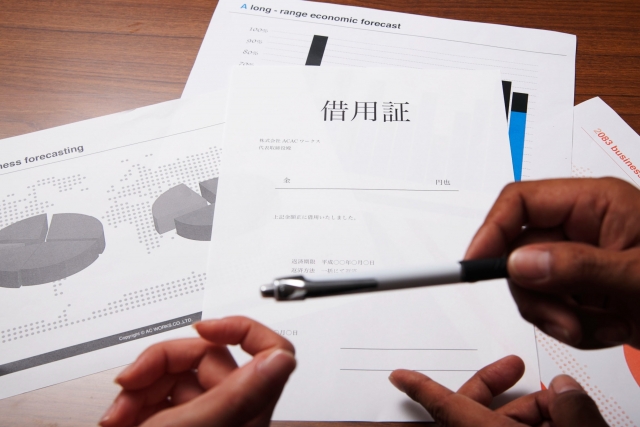貸し借りがあったことを証明する証書を借用書といいますが、貸借の対象が金銭なら金銭借用書、物なら物品借用書を使います。
たとえば金銭が貸し借りの対象の場合には、誰が誰に対していくら貸したのか、いつ返すのかなど取り決めを書面にて記した書類であり、金銭借用書や金銭消費貸借契約書など種類があります。
資金調達の場面でトラブルに発展することを防ぐためにも、もしお金の貸し借りをする場合には借用書を交わしておくことが大切です。
そこで、適切な内容で借用書を作成できるように、すぐにテンプレートひな形として使える金銭消費貸借契約書と借用書のサンプルをご紹介します。
目次
借用書は何のために必要か
資金調達の場面においても借用書の作成を求められることがありますが、これは誰が誰に対し、いくら借りたのか、いつどのような方法で返済するのかなどを証明するために作成されます。
単に借用書とよぶこともあれば、金銭借用書、借用証書といった呼び方をする場合もあります。ただ、いずれもお金を借りたことを証明する書面であることに変わりはありません。
金銭消費貸借契約書とは
金銭消費貸借契約書は、主には銀行などの金融機関や消費者金融会社など貸金業者の貸主からお金を借りて資金調達する場合に交わす書類です。
貸主側が貸し付けを行うにあたり、後に返済を巡るトラブルに発展することを防ぐために作成されます。
そのため金銭消費貸借契約書には、融資される金額、資金の使途、設定される利率、返済期日など、様々な条件が記され、将来の弁済を約束する内容となっています。
借用書がなくても契約は成立する
実は借用書を作成せず、口約束だけでも契約は成立します。しかし口約束で契約できるとしても、お金を借りた側が借りた覚えはないと言い放ってしまえば、貸した側はお金を返してもらうことができなくなりますし、返す意思はあってもいつまでに返済しなければならないと当初約束していたはずなのに、忘れてしまう可能性もあります。
このようなトラブルを防ぐためにも、口頭で合意があった内容を借用書という証拠書面で残しておくことはとても大切です。
また、万一裁判などに発展した場合でも、お金の貸し借りがあった事実を証明できなければ不利な立場にたたされてしまいます。証拠となる書面として借用書を残しておくことで、万一裁判で争わなければならなくなった場合でも有効に活用できるでしょう。
借用書と金銭消費貸借契約書の違いは?
借用書は借主が署名し貸主が保管しておくものであるのに対し、金銭消費貸借契約書は借主と貸主の双方が署名しそれぞれが保管しておきます。お金の貸し借りが終わるまでは紛失しないようにしてください。
お金の貸し借りで使用する借用書の正しい書き方
借用書を作成したくても何をどのように記載していけばよいかわからない場合もあるでしょう。そのような場合に活用したいのがテンプレートひな形やサンプルです。
正しい書き方を知っておくことで、いざというときのトラブル回避に繋がりますので、ご紹介するテンプレートひな形を有効に活用するようにしてください。
借用書の種類を大きく分けると主に次の4種類です。
- ・金銭消費貸借契約(金銭の貸し借りによる取引を証明する書類)
- ・金銭消費貸借兼抵当権設定契約(金銭消費貸借契約に抵当権を加えた取引を証明する書類)
- ・債務承認弁済契約(債務の弁済を約束する書類)
- ・金銭準消費貸借契約(債務を金銭消費貸借契約に切り替える書類)
なお、ここでは一般的に用いられる金銭消費貸借契約書と金銭借用書のテンプレートひな形をサンプルとしてご紹介します。
借用書を構成する項目

借用証として成立するために必要な項目は、
- ・借用証であることを示すための表題・タイトル(金銭消費貸借契約書、金銭借用書といった文言)
- ・宛名
- ・借用金額
- ・事実の認定(金銭受領や貸借の事実の明記)
- ・利息の取り決め
- ・返済期日
- ・返済方法
- ・日付
- ・借主の住所氏名・押印
- ・貸主の氏名
などです。
借用書テンプレートひな形(金銭消費貸借契約書・簡易型)
金銭消費貸借契約書
貸主 ●●●●(以下、「甲」という。)と借主 ▲▲▲▲(以下、「乙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金○○万円を貸付け、乙はこれを受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金○○○○円を平成○○年○○月○○日限り甲方に持参して支払う。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成○○年○○月○○日
貸主(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ●●●●
借主(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ▲▲▲▲
借用書テンプレートひな形(金銭消費貸借契約証書・連帯保証人なし)
金銭消費貸借契約書
貸主 ●●●●(以下、「甲」という。)と借主 ▲▲▲▲(以下、「乙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金○○○○万円を貸付け、乙はこれを受領した。
第2条 乙は、甲に対し、前条の借入金○○○○万円を平成○○年○○月から平成○○年○○月まで毎月○○日限り金○○万円宛分割して、甲方に持参して支払う。
第3条 利息は年○○パーセントとし、毎月○○日限り当月分を甲方に持参して支払う。
第4条 期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年○○パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条 乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を1回でも期限に支払わないとき。
② 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
第6条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成○○年○○月○○日
貸主(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ●●●●
借主(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ▲▲▲▲
借用書テンプレートひな形(金銭消費貸借契約書・連帯保証人あり)
金銭消費貸借契約書
貸主 ●●●●(以下、「甲」という。)、借主 ▲▲▲▲(以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 △△△△(以下、「丙」という。)は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金○○○○円を貸付け、乙はたしかにこれを借受け、受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金○○○○円を平成○○年○○月から平成○○年○○月まで毎月○○日限り金○○○○円也宛合計○○回にわたり、甲方に持参又は送金して割賦弁済する。
第3条 利息は元金に対し年○○%の割合とする。
第4条 利息は、借入日を第1回とし、以後毎月○○日までに翌月○○日までの分を前払する。ただし、平成○○年○○月○○日より、平成○○年○○月○○日までの利息は借入時に支払う。
第5条 期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年○○%の割合による遅延損害金を支払う。
第6条 乙について次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても、乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を期限に支払わないとき。
② 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
第7条 連帯保証人丙は、乙がこの約定によって負担する一切の債務について、乙と連帯して保証し、乙と連帯して履行の責を負う。
第8条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成○○年○○月○○日
貸主(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ●●●●
借主(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ▲▲▲▲
連帯保証人(丙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 △△△△
借用書テンプレートひな形(金銭借用書・簡易型)
金銭借用書
貸主 ●●●● 殿
借用金 金○○○○円也
上記の金額を本日たしかに借用いたしました。
返済期日は、平成○○年○○月○○日とします。
後日のため本書を差入れます。
平成○○年○○月○○日
借主 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ▲▲▲▲
借用書テンプレートひな形(金銭借用書・連帯保証人あり)
金銭借用書
貸主 ○○県○○市○○○○
●●●● 殿
金○○○○円也 ただし利息年○○
上記の金額を私 ▲▲▲▲ は、本日たしかに借受け、受領しました。
ついては、利息は毎月○○日限り、元金は平成○○年○○月○○日限り、いずれも貴殿の住所に持参して支払います。
もし、利息を1回でも期限に支払わないときは、貴殿からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払います。
連帯保証人 △△△△ は、私の債務について保証し、私が上記の債務の履行をしないときは、私と連帯して履行の責を負うものとします。
元金を期限に支払わないときの遅延損害金は、日歩○○の割合とします。
上記を確実に遵守することを誓約し、本書を差入れます。
平成○○年○○月○○日
借主 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ▲▲▲▲
連帯保証人 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 △△△△
まとめ
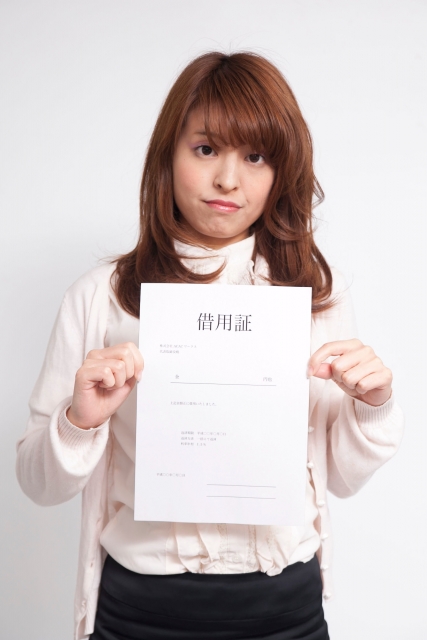
お金の貸し借りでのトラブルはプライベートでもビジネスでも避けたいものです。もし金銭を貸借することがあるのなら、正しい書き方の借用書を作成して契約として交わすようにしておいてください。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。