赤字決算や債務超過など、会社経営が順調といえない状況のときには、何が問題なのか洗い出し改善するための事業再生計画書が必要です。
そこで、事業を再生させるためにはどのような計画書を作ればよいのか、経営改善で必要となることは何かについて説明していきます。
目次
事業再生とは何をすることなのか
事業再生とは、負債総額が資産総額を上回る債務超過や業績不振などにより、経営が困難な状況である企業の事業を再建し、経営の健全性を図ることをいいます。
そのため事業再生は会社再生と呼ぶこともありますが、経営改善契約を立てることがまずは重要です。
事業再生善計画とは
事業再生で重要な「事業再生計画」では、企業が抱える問題点を洗い出した上で経営を改善させる計画を立て、その契約を踏まえて財務の計画を立てていきます。
たとえば銀行など金融機関から融資を受けて資金を調達する場合、銀行が行う企業に対する格付けが重要です。
そして格付けだけでなく、事業再生計画をしっかり立てているか、立てた計画を実現できる見込みなどが融資可否を左右します。
事業再生計画は融資先が行う査定の目安とされるため、誰のためでもなく自社のために策定するようにしましょう。経営の方向性を定め、社員が一丸となり具体化していくことが必要です。
金融機関に事業再生計画を確認してもらったとき、その内容は実現できる見込みが高いと評価されれば、融資を受けやすくなります。
事業再生計画書に記載する項目
「事業再生計画書」には、経営を改善させるために次のような項目について考え、記載することが必要です。
- ・会社の情報
- ・株式
- ・役員情報
- ・組織図
- ・ビジネスモデルの説明
- ・経営改善の内容
- ・事業の方向性
- ・経営改善の施策とスケジュール
- ・損益・財産・キャッシュフローの計画
- ・今後3年の計画の確認について
事業再生計画書は、金融機関から融資を受けるときだけでなく、経営者が今後の経営について考えるときにも活用します。
そのため経営者自身のみで作成しようと考えがちですが、現状を調査してもらい今後どのような予定を立てればよいのか、適切に判断するためにも専門家にアドバイスしてもらいながらのほうがスムーズです。
もし金融機関から融資を受けようとする場合、借入れたい金額が大きいほど、事業再生の難易度は高くなると留意しておきましょう。
金融機関も専門家が調査を行い作成した事業再生計画書だとわかれば、信頼性の高い経営改善計画だと認めやすくなるはずです。
事業姿勢計画書を作成するときのポイント
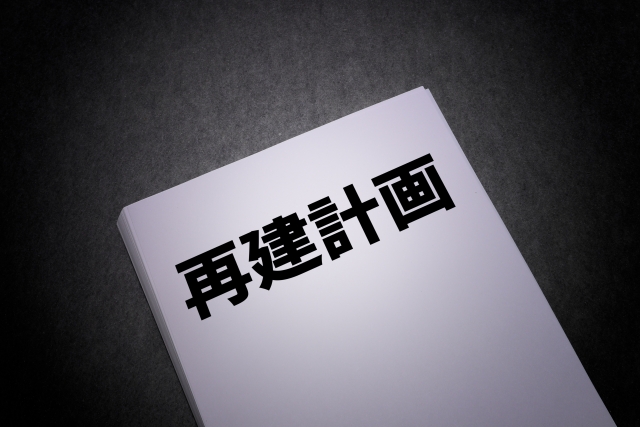
経営を改善させるために事業再生計画書を作成したいのなら、
- ・企業の状況
- ・問題の洗い出しと把握
- ・改善案の検討
という流れでそれぞれの内容を考えていきましょう。
それぞれ詳しく説明していきます。
企業の状況
企業の状況として、
- ・会社の歴史
- ・株主の状況
- ・役員情報
- ・ビジネスモデル(取引先とどのようなビジネスをしているか)
などを記載していきます。
問題の洗い出しと把握
なぜ売上や経営の状態が悪くなったのか、その原因を洗い出しましょう。
目標とする売上高をクリアできていないときには、仮説として考えられる原因を複数出していきます。原因は1つだけでなく、複数の要因が関係していることもあるからです。
改善案の検討
売上や経営の状態が悪化した原因をいくつか洗い出したら、その原因を改善させるための対策を検討していきます。
たとえば売上が低迷した原因が対面販売のみにこだわっていることにあるのなら、インターネットの認知不足を改善させる必要があります。
広告会社に相談することで改善する方法もあるでしょうし、インターネットを使う方法でもSNSの認知不足なら、SNSのコンサルティング会社に運用を依頼すると解決できることもあるでしょう。
できるだけ具体的な改善案を複数出し、その中から最も効果が高いと考えられるものを実施していきます。
事業再生計画書に記載する項目の順番
事業再生計画書には、
- ・会社の現状
- ・改善させなければならない問題
- ・問題となっている原因
- ・原因を改善する具体的な方法
という順番に項目ごとの内容を記載していきます。
事業再生の方法は4つ

事業再生の方法にはいろいろありますが、主に次の4つが挙げられます。
事業再生の方法はさまざまで、下記の4種類あります。
- ・実抜計画
- ・リスケジュール
- ・SWOT分析
- ・整理解雇
それぞれどのような手法なのか、詳しく説明していきます。
実抜計画
実抜計画とは、実現できる可能性が高く抜本的である経営改善のための事業再生計画のことです。
金融庁は実抜計画の要件を定義しており、
- ・実現できる可能性が高いと判断するための要件
- ・抜本的と判断するための要件
の2つに分けることができます。
実現できる可能性が高いと判断するための要件
実現できる可能性が高いと判断するための要件は次の3つです。
- ・計画を実現するために必要な関係者から同意を得ている
- ・計画の中で債権を放棄するといった支援額が確定しており、計画を超える追加的な支援が必要な状況ではない
- ・計画する売上高・費用・利益の予測などに関する想定が十分に厳しい
抜本的と判断するための要件
抜本的と判断するための要件として挙げられるのは、
- ・概ね3年後には金融機関の格付けが正常先になること(中小企業なら概ね5年後)
です。
リスケジュール
リスケジュールとは、資金繰りが苦しく借入金の返済が厳しい状況にあるとき、融資を受けた銀行に申し入れを行うことで当面の返済内容を変更してもらうことです。
リスケジュールを成功させるには、資金繰りが悪化しているため今は借入金の返済が厳しい状態にあるものの、時間的に猶予をもらえれば経営を立て直すことができる見込みが十分にあることが必要です。
リスケジュールのメリット
リスケジュールのメリットとして挙げられるのは、金融機関が条件変更に応じてくれる可能性が高いことです。
銀行などにリスケジュールを申し込み、毎月の返済額を減額してもらうなどの対応をしてもらえたことで、経営状態や資金繰りを改善できた事例も多々あります。
本来であれば守らなければならない当初の返済条件を、リスケジュールにより変更することを銀行が認めることを不思議に感じる方もいることでしょう。
しかし銀行がリスケジュールを認めず、現在の厳しい状態で返済を続けていれば、企業は倒産してしまう可能性が高くなります。
そうなると銀行が貸し付けたお金は回収できなくなり、貸し倒れになってしまうでしょう。
そのため銀行もお金をまったく返してもらえなくなるよりは、リスケジュールにより返済条件を変更したとしても、経営や資金繰りを改善させ返済してもらうことを望んでいると考えられます。
リスケジュールのデメリット
リスケジュールは返済条件を変更してもらう手続のため、借金自体がなくなるわけではありません。
返済までの期限を延長したり毎月の返済額を減額してもらったりなどが目的であるため、リスケジュールに応じてもらった後も経営状態を改善させ財産や負債の整理を行うことが必要です。
企業にとってリスケジュールは時間稼ぎともいえますし、銀行にとっても計上する貸倒引当金を増やすことになるため、応じてもらいやすいとはいえ簡単に認めてもらえるわけではありません。
リスケジュールを成功させたいなら、実抜計画など具体的な内容を提出することが重要です。
リスケジュールを申し込むためにチェックすること
銀行など金融機関にリスケジュールを申し込み、認めてもらうためにも次のポイントを把握しておきましょう。
- ・捻出できるキャッシュフローの金額
- ・キャッシュフローのうち、返済に充てることのできる金額
現在の手元の資金ですぐに準備できる現金の合計額を把握し、その金額から返済に充てることのできる金額を明確にしましょう。
その金額をもとにしながら、資金繰り表や事業計画書を作成し、金融機関に交渉を行います。
なお、借入金の返済が滞った状態でリスケジュールを申し込むと、返済条件を変更しても結局返済されないのではないかと懸念を抱かせてしまいます。
できるだけ返済が滞る可能性がある段階でリスケジュールを相談することが重要です。
SWOT分析

SWOT分析とは会社の経営状態を改善させるための考え方の指針であり、
- ・強み(Strength)
- ・弱み(Weakness)
- ・機会(Opportunity)
- ・脅威(Threat)
の4つの項目を抽出し分析する方法です。
それぞれの項目の頭文字をとって「SWOT分析」という名称になっていますが、「強み」と「弱み」は会社の内部に関するものであり、プラスの項目といえます。
それに対し「機会」と「脅威」は会社の外部に関するものであり、マイナスの項目です。
一般的に、「脅威」があると敬遠される分野に「強み」があれば、その強みを活かすことで競合との差別化を図ることができ、業績を向上させることにつなげることができます。
整理解雇
事業そのものにテコ入れしても事業を再編できないというときには、従業員をリストラするといった整理解雇も検討が必要になることがあります。
整理解雇が認められる要件は主に次の4つです。
- ・人員整理の必要性がある
- ・解雇を回避するために相当の経営努力をした
- ・人選基準が合理的かつ公平である
- ・説明や協議など解雇の手続きが妥当である
整理解雇をすれば人件費などコストを削減できますが、当然デメリットもあります。
デメリットとして挙げられるのは、
- ・退職金を支払うことが必要となるため財務を圧迫する
- ・従業員が解雇に反発し業務に支障が出る
などです。
多くの従業員が納得できる形で整理解雇するためには、実際に人員を整理する前に業務そのものを改善する方法はないか、綿密に検討する努力を重ねることが必要といえます。
単に従業員に対し退職を依頼するだけでなく、整理解雇した後も会社に残り業務改善の協力してもらえる要請するなど、肩たたきといわれる反対の手法も重要となるでしょう。
法的な手法も含めた事業再生の3つの方法

事業を再生させるため、経営改善に向けた計画を立てることが必要です。
しかし事業再生計画を立てて実践しても、再編できないケースもめずらしくありません。
そのようなときには、法的な手法も含めた事業再生には次の3つの方法を検討することになります。
- ・会社更生
- ・民事再生
- ・私的整理
会社更生と民事再生は法的な手続ですが、どの方法が適するかは企業により異なるため、それぞれどのような方法か内容を確認しておきましょう。
会社更生
会社更生とは、会社更生法に基づいて行う手続であり、株式会社しか利用できません。
他の方法よりも費用が高く、期間も長くかかります。手続は裁判所から管財人が選出され進められますが、経営陣は退任しなければならないため注意しましょう。
民事再生
民事再生は、民事再生法に基づき行う手続であり、個人・法人を問わず利用でき、経営陣が退任する必要もありません。そのため会社更生よりも比較的間口の広い手続といえます。
私的整理
私的整理は裁判所を介さず行う事業再生の手続で、債権者である金融機関と直接交渉し行います。
会社更生と民事再生は法的手続であり、すべての債権者が対象となるため、事業再生していることが公になってしまいます。
しかし私的整理では特定の金融機関だけが事業再生していることを知ることとなるため、風評被害などを避けることができます。
望ましい事業再生の方法とは
事業再生は、経営者が自主的に事業を振り返り再生を行うものだけでなく、法的な手続に則り再生を行うものや金融機関と合意を得て行う私的なものもあります。
企業の経営状態で行わなければならない対応策は異なりますが、事業再生計画を立てなければならない企業の原因の多くは、次に集約されると考えられます。
- ・大口の取引先を喪失した
- ・競合先が出現したことで売上と利益が減少した
- ・先代経営者が多額な過去債務を内包していた
- ・本業以外の資金流出や固定化
そこで経営を改善させるためには、
- ・事業改善策(事業・部門の統廃合など)
- ・業務改善策(コスト削減・生産性向上・営業強化・利益極大化など)
- ・財務改善策(資金繰り改善など)
などを立て、改善策をコンサルタントなど専門家に相談し、協業でブラッシュアップを図ることが望ましいといえます。
最終的な計画を策定したら、企業価値を向上するために社員が一丸で取り組むことが求められます。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。





