事業再生は事業の実態を維持できているときに行うことが必要であり、その手順においてもスピード感を持って取り組む必要があります。
企業経営の血液といえる資金が底をつくよりも前に事業再生を行う必要がありますが、限られた時間でどのような手順で進めていけばよいのか解説します。
目次
事業再生とは
事業再生はターンアラウンドや企業再生と呼ばれることもありますが、様々な要因や背景により、厳しい資金繰りで行き詰っている企業が健全経営を目指すプロセスのことです。
その手順の中には、金融機関や取引先などの協力の下で、資金繰りや損益改善を行うことも含まれます。
経営不振の状況から再生させる取り組みなどが事業再生であり、赤字状態からの黒字転換、不採算事業の切り離しなど様々な方法があります。
企業が倒産してしまう主な原因
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、倒産企業が相次いでいる状況ですが、なぜ企業が倒産してしまうのかその原因を把握しておきましょう。
企業倒産で多い理由として挙げられるのが、
- ・経営不振や売上低迷
- ・長期に渡る経営の悪化
- ・資金力の低下による過小な資本での経営
- ・ワンマン経営
- ・取引先の倒産に続く連鎖倒産
- ・過大な設備投資
- ・信用力低下による顧客離れ
- ・売掛金が未回収のまま貸し倒れが発生
- ・技術の遅れやアイデア不足など新商品を開発できない
- ・過剰な在庫の発生など在庫状態の悪化
この中で思いあたることがあれば、すぐにでも改善させる必要があり、該当する項目が多いほど経営危機に陥るリスクは高いといえます。
まだ大丈夫と安心せず、早い段階で経営改善を始めましょう。
事業再生の種類
事業再生には、法的整理と私的整理という種類があり、それぞれ次のような違いがあります。
法的整理
法的整理は、
- ・会社更生
- ・民事再生
などを再建型法的整理といい、どちらも事業再生の1つです。
一定の債権者(すべての債権者全員でなくてもよい)が同意し、裁判所が再建計画を認可することで可能となる手続です。
法的再生の手順
- 私的整理が難しい場合に専門家に相談する
- 事業価値を把握する
- 資金繰り計画・事業計画を作成する
- 法的手続の実行
法的再生のデメリットとして、手続きが公になることが挙げられます。
取引先からの信用力が著しく低下してしまい、マイナスイメージの払拭がむつかしくなります。
私的整理
法的整理でない事業再生を私的整理といいますが、まずは法的再生ではなく私的整理で対応できないか検討しましょう。
私的整理では裁判所が関与せずに、債権者と個別で示談や和解交渉を進めていき、企業再生を図っていきます。
- 私的整理に関するガイドライン
- RCC企業再生スキーム
- 中小企業再生支援協議会スキーム
- 事業再生ADR
- 企業再生支援機構
など、どのガイドラインやスキームを手順として行うかは、再生企業の状況などによって異なります。
私的整理では裁判所に支払う費用がかからず、社会的な信用も低下しないため風評被害などにより企業イメージが損なうことはありません。
また、法的整理より迅速に問題が解決できることもメリットです。
ただしデメリットとして、
- ・債権者によっては交渉に時間が掛かることもある
- ・再建する債権者がいても法的拘束力はない
- ・法的手続でないため裁判所に保全処分を求めることはできない
といったことが挙げられます。
ただ法的整理よりは受けるダメージは少なくてすむでしょう。
事業再生のタイミング

事業再生の関係者として挙げられるのは、
- 株主
- 取締役
- 従業員
- 債権者
- 顧客
- 外部アドバイザー
などです。
株主や債権者は財務的な利害関係者であり、再生価値を最大化できるかを気にすることとなるでしょう。
事業再生計画の承認可否の権限は銀行など金融機関にあり、再生企業にとっても重要なステークホルダーです。
そのため銀行から承認してもらえるように、外部アドバイザーなど専門家と二人三脚で事業再生計画を策定していくことが必要です。
なお、取締役や従業員は雇用維持に関する利害関係といえます。
事業再生を始めるタイミングは、法的整理か私的整理か、どの手続を行うかにより異なります。
ただ一般的には、事業が行き詰まり資金繰りに窮し、銀行など金融機関に対する借入金返済の見通しがたたなくなったときがそのタイミングといえます。
事業再生の手順と進め方
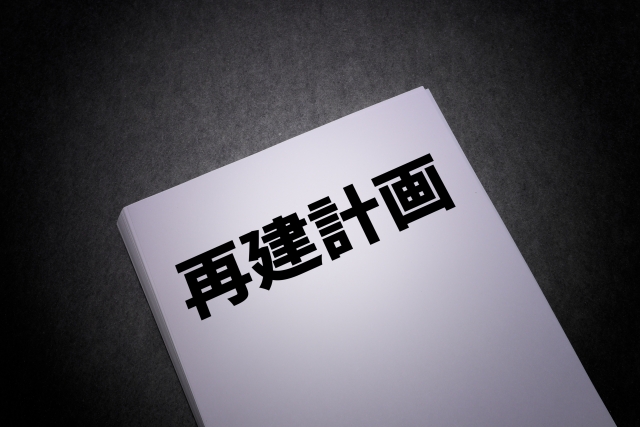
事業再生で必要な手順を進めていく上で、重要となるポイントはどの段階でも資金ショートさせないよう資金繰りを把握することです。
まずは企業の実態を把握する必要があるため、事業や財務面点から現状調査をし、苦しい状況となっている原因を洗い出していきます。
原因の除去を織り込んだ事業計画の策定を行い、金融機関が企業の価値やリスクなどの調査を終わらせた時点で報告します。策定した事業計画が承認されれば、その計画を実行することとなるでしょう。
事業再生の一般的な手順としては以下のとおりです。
なお、資金繰りや債権者の状況などで手順が前後することや、一部省略されることはあります。
1.実態の把握
会社が倒産危機に陥った状況である場合には、
- ・財務内容
- ・資金繰り
- ・銀行ごとの借入金残高
- ・担保状況
などから会社の現在の状況を正確に把握します。
- ・資産・負債の状況
- ・売上規模
- ・損益状況
- ・事業収支
- ・借入先となっている銀行数と借入金額
などを確認し、倒産状態になぜ至ってしまったのか、その原因や将来の事業見通しなど分析しましょう。
2.再生方針の策定
資金繰り表や財務内容などから、債務免除ではなく再生可能となるか判断します。
リスケジュールだけで資金繰り改善が見込めず、債務免除が必要と判断されたときには、どの手法で再生を図るかを検討し方針を決めていきます。
リスケジュールとは
リスケジュールは通称「リスケ」と呼ばれる手続のことで、金融機関に対する借入金返済が難しくなったときに、返済期間の延長や返済額を一時的に減額してもらう交渉を行い応じてもらうことです。
返済可能なスケジュールを立て直すことであり、返済期間・利息・金額の約定変更などを行うことといえます。
3.デューデリジェンス・事業計画案の作成
デューデリジェンスとは、
- ・資産の適正評価
- ・資産や買収対象企業の価値
- ・収益力
- ・リスク
などを詳細・角的に調査・評価することです。
財務内容などを精査し、再生後の事業計画案を作成します。
事業計画書は収益力の見込める事業は残し、赤字となっている事業は廃止するといった販売管理削減の他、使用せず所有したままの遊休資産を売却するなどを行うことが必要です。
これらで収益改善を図ることを柱とし、3年ほどの売上と利益の予想推移を作成することが必要になります。
なお債務免除してもらう事業再生手続でも、スポンサー確保のプレゼン資料として事業計画書は重要ですし、赤字や債務超過の企業が新規融資相談するときにも必要なのでしっかりと作成しておくようにしてください。
4.資金の確保
債務免除を受けず再生可能と判断されたときには、新しく融資を受けて資金を確保することを目指します。
そのため銀行など金融機関と交渉することになりますが、資金調達が実現しそうにないときや、債務免除で再生する必要があると判断されたときにはリスケジュールによる資金確保を目指した交渉になります。
ただ、リスケジュールした場合でも資金繰りが改善されないと考えられる場合には、事業維持に影響の少ない取引先や支払金額が多い取引先などに支払いの先延ばしを交渉することが必要です。
5.スポンサー企業の獲得
事業継続し再生していくためには、信用回復や資金確保が欠かせません。そのためには資金力や信用力の高いスポンサーから新しく信用供与してもらい、信用の補完が必要です。
資金提供をしてくれるスポンサー探しと資金獲得を目指していく必要がありますが、多くスポンサーを獲得できればその分、黒字回復までの時期が早まります。
商品を仕入れるための資金が必要なときだけでなく、仕入先が外国企業で与信を必要とするとき、単独での再生実行では黒字化に転嫁させる見込みがないときには事業再生のスポンサーの力が不可欠です。
6.再生手続の準備
債務免除を受け再生を図るとき、中小企業再生支援協議会を利用するなら初期的相談を行うことが必要です。
私的整理ガイドラインに基づいた処理で再生を図るのなら、メインバンクに初期的相談を行いましょう。
再生の可能性が認められれば、協議会やメインバンクから支援を得ながら再生計画案を作成していくことになります。
法的整理で再生を図るときには、手続申し立てに関する資料作成が必要です。
たとえば民事再生を申し立てるときには、
- ・再生手続開始申立書
- ・事業計画書
- ・債権者一覧表
- ・資金繰り実績
- ・予定表
などを作成しなければなりません。
仮に自社が倒産してしまったら連鎖倒産する可能性のある取引先の買掛金などは、可能な限り手当し連鎖倒産を防ぐ配慮も必要です。
7.再生手続開始
私的整理で再生を図るときには、手順として再生計画案を作成した後に、債権者に再生に至った経緯の説明や謝罪を行います。
説明により理解を得た上で、再生計画の承認を得るようにしましょう。
法的整理で再生を図るときには、更生手続の開始申立後に、従業員や債権者に再生に至った経緯説明と謝罪を行います。
こちらも説明により理解を得る手順は欠かせず、再生に向けた協力と関係の継続・維持をお願いしなければならないでしょう。
今後の事業・弁済計画を主とした再生計画案を作成し、債権者から承認を得ることになります。
8.再生手続の実行と終了
承認を得ることができれば、策定した再生計画案に基づき再生手続を実行していきます。
計画通り、債権者に弁済が実行され終了となります。
事業再生を行うメリットとデメリット

事業再生を行うことはメリットもあればデメリットもあるため、それぞれの内容について把握しておきましょう。
まず事業再生には、
- ・債権者に対し弁済ができること
- ・従業員やその家族の生活が維持できること
- ・取引先との関係継続が可能となること
- ・顧客に対するサービスを変わらず提供できること
といったメリットがあります。
破産してしまえば企業価値や経営者の信頼は大きく低下してしまいますが、今後の事業や経営の改善に繋げることができます。
ただしデメリットとして、
- ・債権者に迷惑をかけてしまう
ことが挙げられます。
返済が遅れてしまうことは、債権者の理解や協力がなければできないことですが、いずれにしても迷惑をかけることには変わりません。
事業を継続できたとしても、経営者自身の精神的なダメージも大きく、労務負担が改善されるまでは周囲からのプレッシャーも強いため緊張状態に耐えることのできるメンタルが必要です。
事業再生を成功させるために必要なこととは?
単独で事業の再生に取り組んだとしても、改善途中で舵取りに失敗してしまい、赤字経営が改善されなければ取引先や債権者にさらに大きな損害を与えてしまいます。
そのため事業を再建させていくためにも、黒字化を見込める計画を立てる段階が重要です。
無理な計画では実行が難しく、周囲まで巻き込み経営者との共倒れになってしまう可能性もあります。
債務が大き過ぎるときや返済はできないと判断されるときには民事再生手続で、信用棄損を最小限に抑えることも必要となります。
ただこの場合にも専門家を味方に付け、もっともよい方法を十分探った上で選択することが求められます。
事業再生の専門家とは?

事業再生の専門家には、財務デューデリジェンスや策定後の事業計画について財務面で支援を行う公認会計士などの専門家もいれば、策定そのものをサポートする中小企業診断士などが挙げられます。
また、財務と事業の両面で支援してくれるコンサルティング会社などもあるため、どの方法を望むかにより相談する専門家も変わってくるでしょう。
一部の私的整理や、民事再生・会社更生などの法的整理なら弁護士などにも相談することが必要になるなど、いずれにしても専門的な知識を持った専門家に相談したほうが安心です。
まとめ
事業再生はその手順においてもスピード感を持って取り組むことが必要であり、私的整理や法的整理などによって必要な手続も変わってくることを理解しておきましょう。
いずれにしても倒産危機に直面した段階で行う手続のため、限られた時間でスピーディに手続することが必要です。事前にどのような手順で進めていけばよいのか確認しておき、自社にとってもっともよい手法を選択するようにしましょう。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。





