未払いのまま放置されている売掛金はないでしょうか。売掛金の回収はスピード勝負のため、遅れれば他の債権者に対する支払いに充てられることとなり、自社には未払いという状態が続いてしまいます。
適切に売掛金が回収できず、未払い状態が続くことで自社の資金繰りにまで悪影響を及ぼすことになっては売上をあげた意味がありません。
そこで、未払いの売掛金を回収するために必要なことを具体的に解説していきます。
目次
売掛金が未払いになったらすぐに行動!
売掛先企業から売掛金の支払いがされず、帳簿上の仕訳処理でいつまでも売掛金が消えない…という場合、気になるのはなぜ遅れが生じているかでしょう。
その場合、まずは売掛先企業に連絡を取って「なぜ未払いの状態なのか」「いつなら支払いが可能か」確認することからはじめましょう。
様々な理由や事情があるでしょうが、いずれにしても未払いという状況に変わりはありませんので、並行して次の対策を講じることが必要です。
売掛金に利息は付きませんが、期日に支払いがなく未払いとなったときには債務不履行となり、遅延損害金(遅延利息)の請求は可能です。
遅延損害金は年率6%ですが、契約の際に利率の取り決めがあればそれに従います。未払いの売掛金に対する遅延損害金は支払期日から発生し、元金と遅延損害金の支払いをしてもらうことになります。
ただし売掛金は民法の改正により一律5年で時効を迎えてしまいますので、それまでに適切に回収できるように早めに行動してください。
未払い分の売掛金について契約書の確認を
未払いの売掛金を無理に取り立てようとすると、反対に刑事告訴されてしまう可能性があるため適切な対応が必要です。
違法な回収にならないためにも、まずは売掛先企業との間で交わした契約内容を確認しておきましょう。
確認する書面は、
- ・売買契約書
- ・発注書・発注請書
- ・基本契約書
- ・見積書
- ・請求書
- ・納品書
などです。
これらの書類の中で、次の項目を確認するようにしてください。
売買代金に対し売掛先企業が捺印した書面はあるか
売買代金が記載された売買契約書や発注書がある場合、売掛先企業の捺印が確認できれば、金額について了承していることを証明できます。
この書面は、後に説明する仮差押えや訴訟など法的な措置で未払分を回収する手続きに重要となります。
ただし売掛先企業との長い付き合いや取引上の慣習などで、見積書や請求書のみの作成ということもあるでしょう。この場合、売買代金に対し売掛先企業が了承したことを証明する書面が手元にない状態となります。
その場合、将来的に仮差押えや訴訟などの法的手続きを行うことも見据え、売掛先企業との間で金額に合意していたことを証明する準備を検討しなければなりません。
基本契約書などに期限の利益喪失条項は盛り込まれているか
売掛先企業が売掛金の支払いを遅れてしまったとき、他にも発生しているまだ支払期日が到来していない売掛金についても支払わなければならなくなることを規定する条項が期限の利益喪失条項です。
売掛金の未回収を防ぐため、売買基本契約書や売買契約書に盛り込んでおくことが必要ですが、この条項の有無も確認しておきましょう。
商品の所有権がいつ移転するか
販売する商品がいつ売り手から買い手に渡り、いつ所有権が移転するのか契約書に記載されている内容を確認しておきましょう。
所有権の移転時期は、商品を引き渡したときと代金を支払ったときのいずれかに設定されていることが多いようです。
代金を支払ったときに移転する契約であれば、未回収の売掛金が発生している状態では所有権は買い手である売掛先企業に移転されていないことになります。
そのため仮に売掛先企業が倒産してしまった場合でも、売買契約を解除し商品の引きあげが可能です。
新たな出荷は停止
未回収の売掛金がすでに発生している状態で、さらに売掛金を増やすことは好ましいとはいえません。そのため新たな出荷は停止し、回収しなければならない売掛金を増やさないようにしましょう。
売掛先企業に対しては、今未払い分として残っている売掛金が入金されるまで、出荷を停止することを伝えるようにします。
未払い分と相殺可能な債権はないか確認
売掛先企業が買掛先でもある場合、まだ支払っていない未払金が発生しているのなら未回収の売掛金と相殺することを検討しましょう。
他にも返品などが発生し返金しなければならない代金や、未払いの仕入れ代金などがあれば相殺することで未回収分を減少させることができます。
もしも相殺可能な債権がある場合、売掛先企業に対して相殺の通知を内容証明郵便で送ることが必要です。
未払いの売掛金回収のため売掛先企業の協力を得られるなら
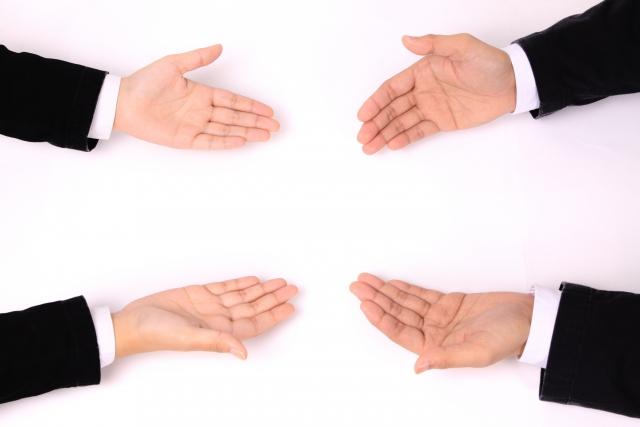
売掛先企業と連絡を取り合うことが可能であり、一定の協力を得ることができるのであれば、未回収の売掛金を支払ってもらう上で次のことを行っておきましょう。
未払金残高確認書を作成しておく
売掛先企業に、未払いとなっている売掛金について未払金残高確認書を作成してもらうように依頼しましょう。
未払金残高確認書は今未払いとしていくら売掛金が残っているか確認してもらうための書類です。売掛先企業が未払いの売掛金があることを確認し作成すれば、未払い分があることを認めたことになります。
念書などを作成してもらうことは難しくても、未払金残高確認書であればスムーズに相談しやすいので、後で法的手続きを取る場面での証拠書類として必ず依頼しておくようにしてください。
決算書を提出してもらうように求める
売掛金が回収できない場合、売掛先企業に決算書を提出してもらうように要求しましょう。決算書を見れば、売掛先企業の経営状況など確認できるだけでなく、現在保有する資産なども知ることができます。
後に差押えなど法的手段を講じる場合にも、どのような資産を保有しているのか把握しておくことは必要です。
商品を引きあげる
売掛先企業の手元に残っている商品があるのなら、売買契約を解除し商品を引きあげるという方法もあります。
ただし売掛先企業が商品の引きあげに承諾していない状態で行うと、窃盗罪に該当することになってしまうので注意してください。
商品引きあげについて承諾を得て、必ずその内容を書面に残しておくようにしましょう。
仮に承諾を得ることができなくても、裁判所で動産引渡断行仮処分という手続きを行うことにより、強制的に引きあげることもできます。
支払口座を変更してもらう
売掛先企業が自社から仕入れた商品を他に販売している場合において、まだ転売先からその代金の支払いがされていないのなら、入金予定分を自社の未払い分に充ててもらうことが必要です。
そこで、転売先から支払いのある入金口座を、自社の口座に変更してもらえないか交渉してみましょう。
債権譲渡担保を使う
支払口座を変更してもらう方法は、売掛先企業が倒産・破産した場合には使えません。
さらに売掛先企業が支払い口座を変更することに了承したとしても、売掛先企業が別の支払い先に債権を譲渡するリスクも否定できないといえます。
この場合、売掛先企業が転売先に対し保有する代金債権を担保に差し入れてもらう債権譲渡担保という方法も可能です。
債権譲渡担保は売掛先企業との間で債権譲渡担保設定契約書を作成すること、さらに転売先に内容証明郵便を使い債権譲渡担保の通知することが必要になります。
連帯保証を要求する
売掛先企業が資産を保有していないものの、経営者に個人資産がある場合には連帯保証人になってもらう方法も有効です。
それによって売掛先企業の資産だけでなく、社長個人の資産から支払いを求めることが可能となります。
売掛先企業に協力してもらないときには未回収分をどう回収する?

売掛先企業が積極的に協力してくれる場合はよいですが、開き直っている場合や連絡が取れない状態では未払い分を支払ってもらうことはできません。
売掛先企業から協力を得られない場合、未払いの売掛金を確実に回収するために次の行動を起こしましょう。
未払いの売掛金を支払ってもらうよう内容証明郵便を送付
売掛先企業に催促しても未払い分を支払ってもらえない場合や協力してもらえない場合には、内容証明郵便を使って支払を督促しましょう。
自社独自で送付することでできますが、弁護士に依頼し弁護士名を記載してもらうとより効果が見込めます。
送付する内容は、支払がないときには法的手段を講じることの警告です。
法的手段という内容はもちろん、弁護士名で送付することで売掛先企業に心理的なプレッシャーをかけることができます。
法的手段で未払いの売掛金を回収
内容証明郵便を送っても反応がない場合には法的手段を検討しましょう。
法的手段で未払いの売掛金を回収する場合、一般的にはまず仮差押えを行った後で、訴訟または支払督促・強制執行などを行う流れになります。
未払いの売掛金回収に向けて財産を仮差押え
売掛先企業が保有する資産がある場合、仮差押えから始めます。
いきなり強制執行しようとしても、先に訴訟を起こし裁判所に売掛金を支払うよう命じてもらう判決を出してもらわなければできません。
仮差押えを先にしておけば、強制執行に至るまでの判決を待つ間、売掛先企業が財産を隠したり凍結したりすることを防ぐことができます。
仮差押えが可能となる資産は、
- ・商品を転売している場合の転売先に対する代金債権
- ・銀行預金
- ・不動産
- ・取引上の債権
- ・法人名義で加入している生命保険
- ・法人名義で所有している自動車
- ・法人名義で取得しているゴルフ会員権
- ・金庫内の現金や店舗の現金
- ・機械などその他の動産
などが挙げられます。
訴訟や支払督促で未払いの売掛金を回収
仮差押え後、売掛先企業に訴訟を起こし訴え、裁判所に売掛金の支払いを命じてもらうことが必要です。
ただ、訴訟より手続きが簡易な支払督促という制度も活用できます。
裁判所から仮執行の宣言が付された支払督促という文書により支払督促をしてもらう制度で、確定すれば判決が出たときと同じ効力を得ることが可能です。
訴訟の場合、自社の所在地の裁判所で審理が可能であることと、売掛先企業の社長が連帯保証人になっているのなら企業と連帯保証人に同時に請求ができます。
しかし訴訟は1度の期日で終了せず時間がかかることがあるので、未払い分を回収するまで一定期間待たなければなりません。
また、弁護士に依頼し裁判所に出向いてもらうことが必要になるなど、別途報酬などが必要です。
それに対し支払督促の場合は、売掛先企業から異議がなければ裁判所に出向く必要がなく、1か月半程で解決できます。
しかし売掛先企業から異議を出た場合には通常訴訟に移行することとなり、売掛先企業の所在地の裁判所で審理を行うことになります。売掛先企業が遠方の場合、遠方の裁判所まで出向かなければならなくなると留意しておく必要があります。
さらに売掛先企業と連帯保証人に請求する場合には、別々に手続きをとらなければなりませんので注意しましょう。
強制執行で未払いの売掛金を回収
訴訟による判決が出た後は裁判所を通して強制執行を行うことが可能となります。
買主が保有する取引上の債権・預金・現金・動産・不動産・生命保険などの資産以外にも、法人税還付金や消費税還付金なども強制執行の対象です。
売掛金の未払いを発生させないために必要なこと
毎月遅れることなく売掛金を支払ってもらうことができれば、未払いの発生に頭を悩ませることもなくなります。
そのためにも売掛先企業との間で契約を結ぶときには、次のように契約書をしっかりと整備し管理するようにしましょう。
売掛金となる金額はしっかり明記する
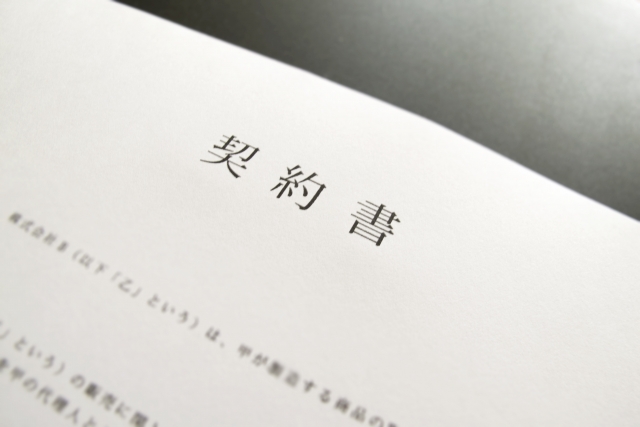
長期に渡り繰り返される取引の場合、それぞれの取引において売買契約書を作成しないというケースも少なくありません。注文書や注文請書なども同様です。
しかし売掛金が未払いになったとき、いざ回収しようとしても発生している代金に対し、売掛先企業が承諾していたことを証明する書面がなければ法的手続きで不利になってしまいます。
馴れ合いのような関係でもけして口頭のみで契約をせず、日ごろから代金が明記された契約書や注文書などを作成する癖を身につけておくようにしましょう。
期限の利益喪失条項は盛り込んでおく
先にご説明した期限の利益喪失条項は売買契約書や基本契約書に必ず盛り込んでおくようにしましょう。
また、売買契約書に記載する商品の所有権が移転する時期について、代金を全額支払われたときであると明記しておくようにしてください。
それにより、売掛先企業が万一破産した場合でも、残っている商品があれば引きあげが可能となります。
商品を特定できる商品番号など記載しておく
商品が売掛先企業から転売されていると、自社には商品の所有権がなく商品を引きあげることはできなくなってしまいます。
この場合、自社に法律上認められる優先権に基づき、売掛金を回収する動産売買先取特権の行使を検討できます。
売掛先企業が破産したときでも優先して売掛金を回収できる方法ですが、契約書に商品を特定するための番号など記載しておく必要があります。
記載がなければ商品の特定が難しくなり、動産売買先取特権の行使の妨げとなってしまいます。
まとめ
売掛金が売掛先企業から適切に支払われず、未払いになってしまうとどのように対処すればよいか迷ってしまうことになります。
しかし本来であれば期日に入金されなければならないお金ですので、少しでも遅れが発生したときにはなぜ未入金なのかその理由を確認し、適切な措置を講じるようにしていきましょう。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。





