売掛金とは、商品やサービスを販売や提供したときに生じる、代金を受領する権利のことです。現金ではなく手形を使った支払いがなされれば受取手形として、それ以外は売掛金として処理されます。
企業活動における取引の金額が大きくなるほど売掛金の額も増え、代金が回収されるまでの期間の資金繰りに影響を及ぼしやすくなってしまいますので、確実に回収する必要のある債権であると捉えておく必要があります。
そこで、売掛金という債権をどのように回収していけばよいのか、万一回収できない場合はどうすればよいのかご説明します。
目次
売掛金の有無は個人や企業の損益に大いに関係する
売掛金とは、売上が発生したときには入金されず、後になってその代金がしはらわれるお金であり、いわゆるツケ払いに該当するものです。
当月に売上として計上されていても、肝心の代金は翌月以降でまだ回収されていない状態を示すため、会社の手元の資金にも影響を及ぼしやすい部分でもあります。
もし売掛金が取り決めていた期日を迎えも支払われていないのに、そのまま何もせずに放置しているとどうでしょう。相手の売掛先企業は、「何も言われていないからまだ支払わなくてもよいだろう…。」と勝手に安心し、さらに支払いを行わなくなるかもしれません。
特に金額が多いと、入金されない売掛金が原因で手元の資金が不足し、支払いのために借り入れを行わなければならなくなったり、支払いできず取引先の信用を失ったり、最悪の場合は資金がショートしてしまい倒産するといったことも考えられます。
さらに売掛金の回収ができず、資金繰りが悪化して銀行などから金銭の管理能力が低いと判断されてしまうと、今後、成長や伸びが見込めないとマイナスの評価を受ける可能性も出てきます。
そうなると、いざ設備投資で銀行融資を受けたい!という場面において、非常に不利になると理解しておきましょう。
売掛金という債権を回収するには
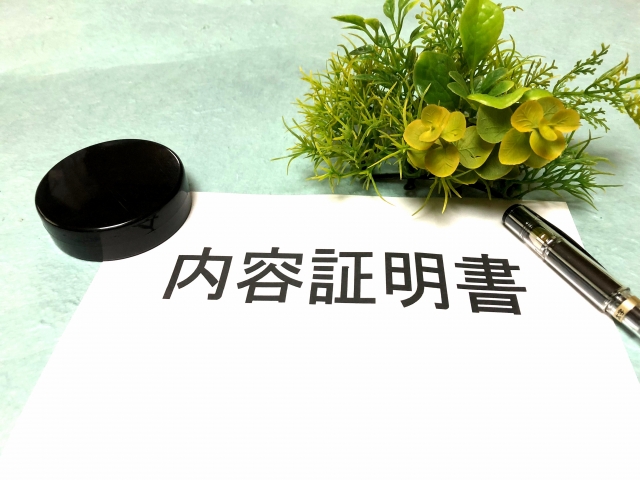
もし売掛先から売掛金の支払いがなく、売掛債権が残ったままの状態であれば、どのように回収するか考えなければなりません。
売掛金を回収するには次のような方法があるので、今後の売掛先との取引も含めた上でどの手段で債権回収を行うか決めるようにしましょう。
内容証明郵便による回収
仮に売掛債権の回収ができないことを弁護士などに相談した場合、内容証明郵便を送ることを提案されることがほとんどです。
内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に対して、どのような内容の手紙を出したのかを、郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。
売掛金の回収方法としてはポピュラーな方法ですが、実際のところ法的な効力はありません。ただ、売掛先から手紙は受け取っていないとごまかされる心配はなくなる上に、弁護士など専門家を経由して送付することで圧力を与えることは可能です。
交渉による回収
内容証明を送付したのに、特に売掛先から何の行動も見られない場合には、直接交渉して回収することを検討しましょう。
本来であれば、売掛先との関係が悪化することを極力避けることができる方法なので、内容証明郵便を送るより前に行いたい方法です。
相殺による回収
もし売掛先との間に、売掛金だけでなくこちらが支払っていない仕入れ代金(買掛金)なども存在する場合には、売掛金と買掛金を相殺して回収する方法も検討できます。
商品の引きあげによる回収
すでに販売している商品をひきあげる形で回収することもできますが、同意を得ずに行うと窃盗罪に問われることになるで、必ず相手の同意を得た上で実行する必要があります。
債権譲渡による回収
売掛先が保有している第三者の売掛債権を譲渡してもらう形でも回収することはできます。
訴訟による回収
なるべく避けたい方法ですが、いずれの方法でも売掛金の回収が見込めない場合、次の法的手段で回収を検討することとなるでしょう。
●支払督促
正式な裁判手続を経由せず、申立てに基づいて簡易裁判所の書記官から売掛先に金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。相手からの異議申立てがなければ、判決と同じ法的効力を得ることができます。
●民事調停
裁判所の調停員会が仲介人となり、双方の主張を調整しながら話し合いで円満に和解を図る非公開の手続きです。調停で合意されると、判決と同様の法的効力を得ます。
●少額訴訟
原則、1回の審理で判決される迅速な手続きで、60万円以下の金銭を求める場合に利用できる訴訟です。
●民事訴訟
裁判官が法定で双方の言い分を聴き、さらに証拠を調査して最終的に判決で解決を図る方法です。
売掛金は時効を迎えると消滅してしまう

売掛金が回収できなくても、金額がそれほど大きくなく、資金繰りにもそれほど影響を及ぼしていないので、そのうち支払ってもらえるだろうと安易に考えていると回収できなくなる可能性があります。
実は売掛金にも時効というタイムリミットがあり、発生して一定期間経過すると消滅時効となって売掛金は回収されることなく消滅してしまいます。
なお、売掛金は債権の種類によって消滅時効を迎えるまでの期間が異なりますので、現在回収できていない売掛金の内容に注意が必要です。
1年で消滅するもの
宿泊料や運送費、飲食代金など
2年で消滅するもの
月謝(教材費など)や製造・卸売・小売業の売掛代金など
3年で消滅するもの
診療費、建築代金(設計費含む)、自動車修理費、工事代金など
5年で消滅するもの
上記以外の売掛金
時効まで時間がない!そのような場合は中断の手続きを
売掛金に時効がることを知らず放置していたので、消滅時効まで時間がないという場合でも、次の手続きを行うことで迎える時効を中断させることが可能です。
請求
売掛先に対し請求を行うことで時効を中断させることができますが、訴訟など裁判手続きを含めた請求であることが必要です。
訴訟を行う、または簡易裁判所に支払い督促や調停を申し立てる、訴状提出前に即決和解を行うといった方法があります。
なお、即決和解は裁判所を通さずに行うため余計な費用が発生しませんが、和解が成立しなければその日から1か月以内に訴状の提出を行い、時効中断の効力を回復させる必要があります。
また、裁判前に売掛代金を請求する内容の書面を内容証明郵便で送ることで、相手に書面が届いた日から6か月は時効を中断させることができます。その期間内に何も行わなければ時効は中断の効力を失うので、売掛先から何のアクションもみられなければ裁判などの手続きに移行する必要があります。
内容証明郵便を送り、さらに6か月以内に再度内容証明郵便を送るといったことで時効を延長させることはできないので注意しましょう。
差し押さえ(仮差し押さえ、仮処分)
訴訟や支払催促などで、裁判所が強制執行の許可を出した場合、売掛先の財産を差し押さえることができるようになるため時効は中断します。
ただし、すべての財産を一気に差し押さえることができるわけではなく、判決前に預金などを拘束することになることから、売掛先に対する配慮も必要となってきます。
差し押さえを希望する金額の3割程度を担保金として準備することが一般的ですので、自社にもリスクがある方法と理解しておいたほうがよいでしょう。
債務の承認
裁判手続きを行わなくても、売掛先が債務の存在を認めることによっても時効は中断します。売掛金の一部を支払ったり、支払期間を延長して欲しいと要求してきたり、支払い約束証に対する署名など、どれも承認したこととみなされ時効は中断するとこになります。
売掛金を債権として残さない管理を
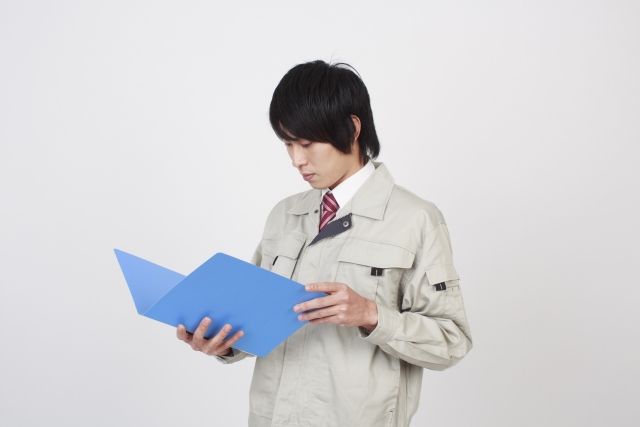
売掛金は、その代金を回収してはじめて利益となり、商売として成立します。売上があがっただけで回収できなければ意味がありませんので、適切な管理を行うようにしましょう。
売掛先の信用調査を
売掛先の経営や資金状況など、発生した売掛債権を支払う能力があるのか信用調査を行うことも必要です。
与信枠の設定
いくらまでなら売掛債権として売掛金での取引を認めるのか与信枠を設定しましょう。もし与信枠を超える取引を行う場合には、先に代金一部を支払ってもらうなどの対策も必要です。
売掛先ごとの管理を
売掛先ごとに、いつ、いくらの売掛金が発生し、いつ回収予定か、さらに与信枠はいくらで設定しているかを一目で確認できる売掛金元帳を作成しましょう。
まとめ
売掛金はその代金を請求することができる売掛債権という名の権利です。もし回収できなくなれば、自社の資金繰りに悪影響を及ぼすため、支払ってもらえない場合には先に述べたような方法で回収を検討することも必要になります。
ただし、今後の取引やこれまでの付き合い上、法的手続きなどが難しいという場合には、売掛債権を売却するという形で事前に貸し倒れリスクを回避することも検討してみましょう。
売掛金は回収までの期間が空いてしまうとさらに回収しにくくなります。そうなる前に早急に手を打つことが大切です。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。






