これから起業し新しいビジネスモデルを展開しようと考えているスタートアップ企業やベンチャー企業などは、どのように資金を調達するのか考えていくことが必要です。
検討の段階で資金調達の指標である「ラウンド」を目安にする方法がありますが、現在スタートアップ企業がどのような段階なのか知ることができます。
そこで、スタートアップ企業が把握しておきたい、「資金調達ラウンド」や「投資ラウンド」と呼ばれる指標についてご説明します。
目次
スタートアップ企業は今どのラウンドにいるのか
「資金調達ラウンド」とは「投資ラウンド」とも呼ばれており、投資家が企業に投資する際の目安となる考え方のことです。
企業に投資をする段階を示すため、その指標は投資家だけでなくスタートアップ企業などが成長戦略を検討する際にも有用です。
そもそも投資家が企業に出資する目的の1つは、投資したときよりも株価が値上がりしたとき、売却すれば利益を得ることができるからといえます。
そこで投資家に向け、スタートアップ企業が今どのような段階あるのか把握しやすいようにあらわしたものが「ラウンド」という考え方です。
「資金調達ラウンド」の5つの段階
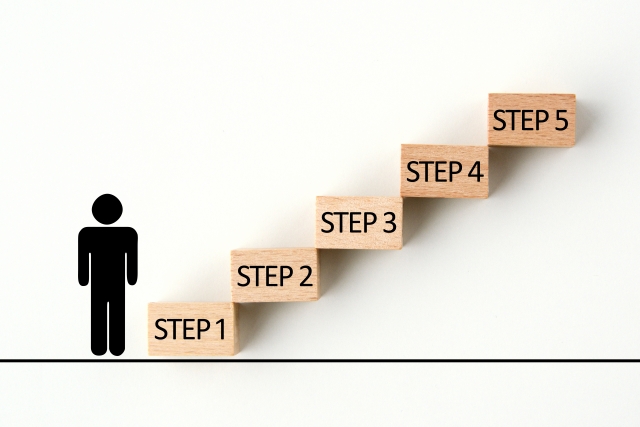
資金調達ラウンドは次のように5つの段階に分かれており、その段階は「フェーズ」や「ステージ」とも呼ばれています。
- ・シード…起業前の段階
- ・アーリー…起業直後の段階(スタートアップ段階)
- ・シリーズA(エクスパンション)…事業を本格的に開始する段階
- ・シリーズB(グロース)…事業が軌道に乗り始めた段階
- ・シリーズC(レイター)…事業で 黒字となり経営が安定しつつある段階
それぞれの段階について以下のとおりご説明します。
シード(スタートアップ前の段階)
ラウンドの第一段階であり、まだスタートアップする起業前の状態をあらわします。
販売する商品や提供するサービスをリリースすることに向け準備を行っている段階であり、市場調査・会社設立・人件費などに充てる数百万円程度の資金を必要とします。
この段階の資金調達先を投資家に限定すると、エンジェル投資家などが挙げられるでしょう。
アーリー(スタートアップ直後の段階)
起業した直後の段階であり、スタートアップ段階を示します。
事業を開始しても、すぐに収益を得ることは難しく、実際には軌道に乗るまで赤字経営の状態になる企業は少なくありません。
事業を軌道に乗せるまで、設備資金・運転資金・ライセンス使用料・販売促進費・人件費など発生するコストも増えるため、常に資金繰りを頭に入れておくことが必要です。
この段階では金融機関からの融資や国・自治体の補助金・助成金などの活用が可能であり、その他ベンチャーキャピタルからの出資なども受けることが可能となる場合もあります。
シリーズA(スタートアップ後の成長段階)
本格的にスタートさせた事業により、だんだんと顧客が増え収益を得ることができるようになるなど、スタートアップ後の成長段階を示します。
商品やサービスなどがリリースされ、認知度を拡大させる市場調査やマーケティングなどにも拍車がかかっていく段階です。
しかし十分に軌道に乗ったとはいえない段階のため、売上を向上させる上で必要な人材雇用や設備投資など、様々な資金も必要となります。
資金調達の規模が数千万円から億単位でかかる時期を示すともいえますが、ベンチャーキャピタルから出資してもらいやすいステージでもあります。
シリーズB(事業が軌道に乗り始めた段階)
事業がいよいよ軌道に乗り始めた段階であり、収益も伸び経営が安定してきた状態を示します。
会社規模を拡大させるため株式上場など検討する企業も出てくる段階ですが、前段階よりもさらに設備投資・広告宣伝費・人材確保などの資金を必要とするため、資金調達の規模もいっそう大きくなります。
出資を受けて資金調達するならベンチャーキャピタルからがその大半を占めることとなりますが、黒字化を実現可能とするビジネスプランを強く示さなければ投資してもらえません。
シリーズC(黒字で経営が安定しつつある段階)
投資家がスタートアップに投資する目的であるエグジット(投資家などが投資資金を回収する方法)をするため、十分な利益・売上の確保など安定した黒字経営が求められる段階といえます。
さらなる事業展開や海外進出、買収といった変化を検討するには多額の資金が必要となり、資金調達する金額も10億円を超える場合もあるほどです。
重要なのは「シード」とスタートアップ時期の「アーリー」の資金調達手段

起業前と起業した直後には、法人設立費用や運転資金、人件費といった様々な資金が必要となります。
資金は必要なのに収益を得ることができず、さらに事業も軌道に乗っていなければ資金不足に陥ってしまうのも無理ないでしょう。
そこで資金調達が重要となりますが、それぞれのステージごとに適した方法を選ぶことが大切です。
シード段階で適した資金調達手段
シードでは事業そのものがまだ開始されていないスタートアップ前の段階です。
そのため資金調達に銀行からの融資を頼ろうとしてもまず審査が通らない可能性があります。
そこで、政府系金融機関である日本政策金融公庫に相談することや、個人の富裕層や元起業家が投資家として出資してくれるやエンジェル投資家などから資金調達する方法が検討されます。
投資会社であるベンチャーキャピタルなども方法として考えられますが、特にシード専門に投資しているケースでは、経営に関してのノウハウやアドバイスなどのサポートも受けることができます。
そして最近もっとも注目されているのがインターネットを通じて資金を集める「クラウドファンディング」です。
事業計画をネットで広く露出することで、将来性を見込んだ個人から少額資金を集めていきます。クラウドファンディングにもいろいろ種類がありますが、株式と交換する投資型もあるため、スタートアップ企業などはケースに応じて選択するとよいでしょう。
シード期で調達したい資金の額
シード期で調達しておきたい資金の額は500万円から1千万円が目安です。
それほど多額の資金は必要といえない時期ですので、エンジェル投資家にもアプローチしやすい段階です。
ただ、第三者に出資してもらう割合が高くなれば、経営方針などに口を出される可能性も大きくなるため出資してもらうのは1~2割程度におさめておくようにしましょう。
また、日本政策金融公庫から無担保・無保証人の新創業融資制度で融資を受ける場合には、創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金を準備しておく必要があります。
資金を調達するまでどのくらいの時間がかかる?
エンジェルと日本政策金融公庫のどちらから資金を調達するかによりますが、おおよそ2か月程度はかかると考えられます。
なお事業ビジョンが明確になっていなければ投資家に出資してもらうことは難しいですし、事業計画書なども作成できず融資を受けることもクラウドファンディングでも資金を集めることはできなくなると留意しておくべきです。
スタートアップ段階であるアーリーに適した資金調達の方法

起業直後では先行投資に資金がかかるため、赤字経営になることが多くなります。
追加で出資してもらうのか、銀行から融資を受けるのか検討が必要となりますが、この段階でも銀行融資は期待できません。
さらに起業前より企業リスクは高くなっていることから、投資家にはさらに質の高い説得力の感じられるビジネスプランを提案できなければ、出資してもらうことも難しくなります。
政府系金融機関の日本政策金融公庫などに相談してもよいですが、あくまでも借金なので返済負担がかかります。返済不要の公的支援制度である補助金や助成金などの要件に該当する場合には、そちらを検討したほうがよいでしょう。
また、最近中小企業などに注目されつつあるのが、保有する入金前の売掛金(売掛債権)を売却し現金化するファクタリングです。
ファクタリングはお金を借り入れる方法ではないため、審査も早く迅速な資金調達が可能となる方法といえます。
信用情報に影響しない点でも、民間銀行と関係を深めて融資を受けたいと考えるスタートアップ企業に有用といえるでしょう。
どのくらいの資金を調達しておくべき?
スタートアップ段階のアーリー期に調達しておきたい資金の額は、2千万円から5千万円が目安です。
設備投資や運転資金などの資金を必要とする上に、これから本格的に事業を軌道に乗せていくための人材確保にもお金はかかります。
スタートアップ企業が土台を作る大切な時期なので、手元の資金が不足しないように適切な資金調達が求められる時期と認識しておきましょう。
資金を調達するまでの時間
会社設立から間もない段階であり、まだ売上は安定していないはずです。
融資を受ける場合には事業計画や見積書との整合性の確認も必要となるため、提出する書類も増え審査も入念に行われます。また、補助金や助成金も同様に複雑な申請を経て、入金まで時間がかかります。
審査に数か月の時間がかかるため、急いで資金が必要なときにはファクタリングなどで一時的な資金調達をしておくなど、手元のお金を枯渇させない対応も必要となるでしょう。
スタートアップが資金を調達するときに考えておきたいリスク

スタートアップ企業が資金を調達するとき、どの手段を使う場合でも伴うリスクは把握しておくべきですので、どのようなリスクがあるのかそれぞれの方法ごとにお伝えします。
出資を受けて資金調達する上でのリスク
投資家などに出資してもらえば、返済不要の資金を調達できるためメリットは大きいと感じるものでしょう。
しかし経営権を外部に握られることや自由度が低下することは留意しておくべきです。
投資家が株式の一部を受け取り、その割合が大きくなれば経営権を握られてしまう可能性が高くなります。議決権の過半数は確保しておくことが必要ですが、状況により必要株式比率は変わるため、20~30%保持で実質的に会社支配を可能となることもあります。
それにより経営が円滑に進まなくなれば、自分が思い描く事業に発展させることができなくなる可能性も出てくるでしょう。
さらに投資家ファンドは10年程度で満期を迎えることとなり、利益(リターン)を付け資金を返還することになります。満期を迎えるよりも前に軌道に乗せておかなければならないと理解しておいてください。
融資を受けて資金調達するときのリスク
融資を受けて資金を調達するときのリスクとして挙げられるのは、そもそも審査が厳しく資金調達につながらないこと、お金を借りることができたとしても返済負担が重くなることが挙げられます。
日本政策金融公庫や銀行から融資を受けるのなら、金利は低く長期で返済することも可能です。しかしノンバンクのビジネスローンなどからお金を借りてしまうと、高金利のため返済負担が重くなり、資金繰りを悪化させるリスクが高くなります。
お金を借りれば必ず返済しなければなりませんので、事前に返済計画を立てた上で無理のない経営が可能か判断することが必要です。
保有する売掛金を売却して資金調達することのリスク
売掛金を現金化するファクタリングの場合、ファクタリング会社に支払う手数料が割高になる点は注意しておきましょう。
期日を待てば取引先から満額入金される売掛金を前倒しさせるため、手数料分、入金額は目減りします。
繰り返し利用を続ければ資金繰りが悪化してしまうリスクを高めるため、利用する期間を事前に決め資金繰り改善を目指すことが必要です。
まとめ
スタートアップ企業が資金を調達する方法はいろいろありますが、どの方法でも共通していることは企業の信用力をアップさせることが大切ということです。
出資してもらう場合や融資を受ける場合はとくに信用力が重視されますので注意してください。
ファクタリングは売却する売掛金(取引先)の信用力が大切となる資金調達の方法なので、スタートアップ企業の信用力はそれほど重視されません。
しかしファクタリング会社との信頼関係を築くことは重要なので、どの資金調達方法を選ぶ場合でも信用力は不可欠と考えておくべきです。
資金調達はスタートアップ企業の段階ごとに適した方法が異なりますが、まずは今どのステージにいるのか把握し、どのような資金調達方法があるのか確認した上で選ぶようにしましょう。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。





