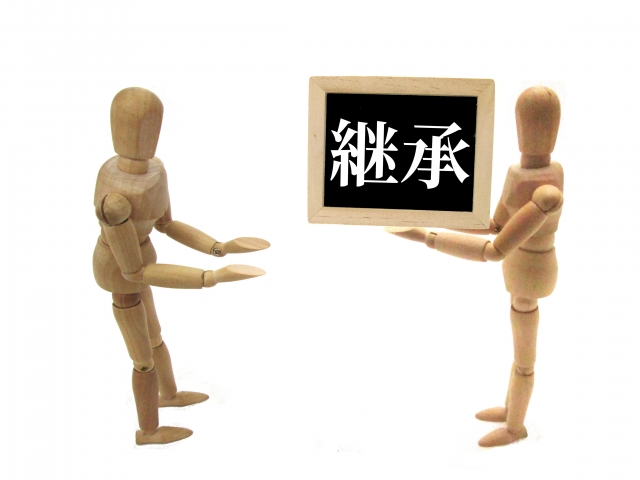中小企業の経営者の多くが事業承継について悩みを抱えていますが、成功させるためのポイントを押さえておきましょう。
事業承継は、誰に会社を引き継いでもらうかによりその方法は異なるため、それぞれポイントも違ってきます。
具体的に事業承継の方法として挙げられるのは、
- ・親族内承継(子や配偶者に対する承継)
- ・親族外承継(従業員や役員に対する承継)
- ・第三者への承継(M&A)
ですが、いずれもメリット・デメリットを理解した上でポイントを押さえ意思決定することが必要です。
そこで、中小企業が押さえておきたい事業承継のポイントについてご説明します。
目次
事業承継で引き継ぐ要素は3つ

近年では後継者不足により、誰に会社を引き継いでもらうのか悩みを抱える中小企業経営者も少なくありません。そのため、M&Aなど第三者に対し事業を譲渡する非同族の事業承継が少しずつ増えています。
日本では人口そのものが減少しているため、今後さらに厳しい環境に置かれる中小企業も増えていくと考えられるでしょう。
そもそも事業承継とは、ヒト・モノ・カネという3つの要素を後継者に引き継ぐことであり、モノとカネを承継することが物的事業承継で、ヒトの承継は人的事業承継といいます。
どちらもスムーズに引き継ぐためには、まず会社の現状を分析し障壁となる問題部分を洗い出していくことが必要です。
その上で、引き継ぐ株式の対策などを検討することも必要となりますが、いずれにしても事前に入念な準備をしておくことが求められます。
そこで、モノとカネを後継者に承継する物的事業承継と、ヒトの承継である人的事業承継のそれぞれの視点から何をポイントとして押さえておく必要があるかご説明します。
物的事業承継のポイント
モノとカネを後継者に承継することを物的事業承継といいますが、現経営者が所有する会社の株式や、会社の土地・建物・設備・運転資金などの財産を承継することです。
特に自社株式を後継者に引き継ぐことは事業承継で重要で、税務上定められている一定の評価方法による評価額で課税されます。
後継者が相続人であれば相続税、贈与という形での承継なら贈与税が課税されますが、後継者の手元に評価額に見合う現金がなければ納税できず事業承継が進まないといった問題も起きてしまいます。
自社株式だけでなく、中小企業の場合には会社の土地・建物・設備などが現経営者個人名義になっていることもありますし、金融機関からの借入金に現経営者の個人保証がついていることも少なくありません。
また個人所有の土地を担保として差し入れていることもあるため、このようなケースでは事前に対策を講じておかなければ、いざ相続が発生したときに相続人を大きく混乱させてしまいます。
相続を争族にしないためのポイント
相続人に対する事業承継の場合、相続を争族にしないためには生前に後継者に贈与・譲渡するといった対策も検討できます。
生前贈与は現経営者の意思で財産の引き継ぎを好きなタイミングで実行できる点がメリットですが、贈与税は相続税よりも税率が高いことがデメリットです。
後継者に自社株式を売却するのであれば、売った株式は相続財産から外れるものの、譲り受ける側が株式購入する資金を保有している必要があります。
人的事業承継のポイント
ヒトを引き継ぐ人的事業承継で後継者に引き継ぐのは、
- ・組織の中での会社社長という役職・役割
- ・会社の経営権
です。
他にも経営理念や信用力、会社独自のノウハウなど目に見えない経営資源も人的事業承継に含まれます。
中小企業の経営では、営業・経理・財務・生産管理など、経営者個人の資質・能力・人脈などに依存していることが多いため従来までの経営を後継者に求めることは難しいといえます。
経営者に権限が集中していることも少なくないため、1人何役もこなしてきた経営者の事業承継では、後継者が同じやり方で同等の能力を発揮しにくいと留意しておくべきです。
ただ、周囲の支えや協力がしっかりしていれば、引退した経営者と同様に事業を動かすことが可能となり、社内をまとめていくこともできるでしょう。
そのためにも現在の経営スタイルやこれまでの現経営者の役割を客観的に見える化し、次世代の経営陣と新たな経営者で検討することが必要です。
事業承継計画についても、会社を引っ張っていく存在となる後継者だけでなく、それを支える人材育成・配置も含めた上で策定していきましょう。
事業承継計画を策定・作成しておくメリット

トラブルを未然に防ぎ事業承継を進めていくためには、事前に事業承継計画を策定し事業承継計画書を作成しておくことが必要です。
事業承継計画書をもとに事業承継を進めていくことが必要となりますが、事前に作成しておくことで次のようなメリットがあります。
ことをポイントと押さえた上で策定・作成していきましょう。
現状を把握しながら事業承継を進めることができる
事業承継計画書には、今後、事業承継をどのように進めていくのかスケジュールも記していきます。
何年後に何をするのか、次のアクションはその何年後に行うのか、仮に計画を立てていても頭の中で描いているだけでは実行できません。
そこで、事業承継計画書にその内容を明記しておくことで、通常業務を行いながら準備を進めていきやすくなります。
そしてヒト・モノ・カネなど、今の会社の状況を把握することで前もって行わなければならないことも知ることができるでしょう。
その過程の中で、何をいつまでに行う必要があるのか明確にできます。
親族や後継者とも話し合いを進めていけば、周囲から理解を得た上で事業承継の計画を立てることができるため、トラブルを防ぐことにもつながるでしょう。
そして、実際に事業承継を進めていく上で、事業承継計画書に記載したスケジュールと照らし合わせ計画どおりに進んでいるか確認できます。
仮に遅れが出ていればその原因を洗い出し対策を練ることが必要となり、予定より先に進んでいれば急ぎすぎていないか再考するきっかけにすることができるでしょう。
経営者と後継者の認識の擦り合わせが可能になる
事業承継計画書にはリストアップした後継者を記載することが必要なので、会社を譲渡する現経営者と譲り受ける後継者の心構えが整いやすくなり、目標を具体化させ的確に行動できるようになるでしょう。
現経営者のみの考えだけで事業承継を進めていくことは難しいため、もし後継者が事業承継を望まないときには無理に会社を継がせることもできませんし、経営方針に納得していないのに押し付けることもできません。
仮に無理に会社を引き継がせることになれば、後継者が今の会社を変えようとそれまで築き上げた実績も無視した改革を行うことになりかねないため、その結果、従業員や役員から不満が出たり反感を買ったりというリスクも発生します。
また、株式譲渡などの資産や企業経営に対する展望など盛り込んでいくことで、現経営者と後継者の意思を確認し合うことができます。
今後の経営で意見が食い違う部分について、議論を重ねながら文書にまとめていくことで、よりスムーズな事業承継が可能となるでしょう。
事業の状態を客観的に見直せる
事業承継は後継者に事業を継いでもらえば終わりではなく、事業承継後の会社や事業に将来性は見込めるのか、現在抱えている負債をどのように解消させていくのか考えていく必要があります。
企業の経営状況を客観的に見直すことが必要なため、事業承継計画書を作成することはそのタイミングと考えるべきです。
変化する社会情勢の中で会社が生き残りをかけ発展していくために、今何をすればよいのか、今後立てていく必要のある対策などを検討する機会となるでしょう。
外部から理解を得ることが可能となる
事業承継計画書を作成することで事業を承継するまでのロードマップを明確化でき、会社の現状を記すことで経営者の家族や雇用されている従業員・役員、取引先や金融機関など外部からも協力を得やすくなります。
経営者独自で事業承継を考えるよりも、様々な人たちから協力を得やすくなることで、より適切な計画を立てることが可能となるでしょう。
会社の今後や後継者から信頼を得ることにもつながり、これまでと変わらず支援を受けやすくなるメリットがあります。
事業承継計画書を作成するタイミング

事業承継を進めていくためには事前に事業承継計画書を作成することが大切ですが、作成に至るまでの準備が欠かせません。
事業承継のスケジュール・会社の今後の見通し・相続人に対する事業承継ならその進め方なども記載していくことになります。
会社が今どのような状況にあり、現経営者の資産や複数いる相続人に対しどのように配分するかなど、様々なことを決めておかなければ事業承継計画書に記載はできないでしょう。
現在の会社の売上高・仕入高などキャッシュフローはもちろんのこと、雇用している従業員の数、業界での会社の立ち位置や事業の将来性など様々なことをまずは再確認してください。
現経営者の資産には個人の預貯金や不動産、株式などが該当しますが、この中で後継者がどれを引き継ぐのか考える必要があります。
そして後継者以外の相続人には何を残すのか決めておかなければ、相続人同士で公平さが失われ相続をめぐる紛争が起きてしまいます。
事業承継の方法により、事業承継計画書作成前に様々な項目を決めておく必要があることを、改めて認識しておいてください。
事業承継計画書を作成する上でのポイント
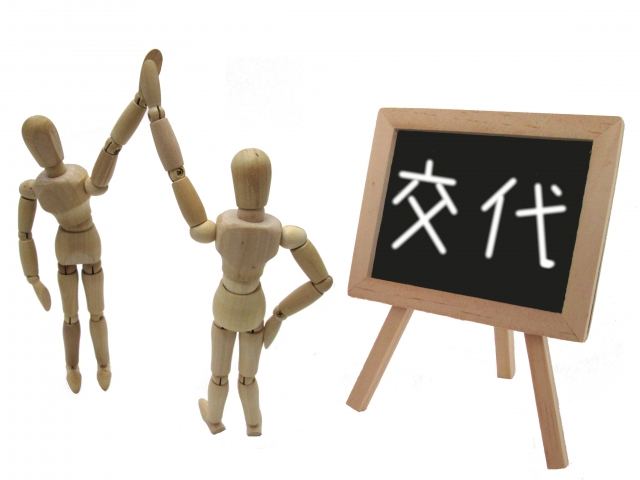
実際に事業承継計画書を作成するにあたり、具体的にどのような内容を記載していくことになるのか、そのポイントを押さえておきましょう。
記載する内容は、大きく分けると次の4つの項目です。
事業承継の大枠について
現経営者・後継者の氏名・年齢・続柄・承継時期・その方法などを記載していきます。
経営理念と中長期的な見通しについて
経営理念はこれまでの理念を再確認し、後継者に引き継いでもらうために記載します。
また、事業承継後に事業をどのように発展させていくのか、現実的な目標数値をもとに中長期の見通しを記載しておきましょう。
事業承継の進め方と主な対策
事業承継では、
- ・関係者に周知し理解を促すこと
- ・後継者教育を行うこと
- ・株式や財産を後継者に譲渡すること
が必要です。
それぞれ、いつ・どのように進めるのか記載しておくと、実際の流れがつかみやすくなります。
年数計画を一覧で示す
いつ何を行うのか、年次ごとに行うべきことを一覧で示しておくとよいでしょう。
売上・利益目標や、人事の予定、事業拡大計画なども記載しておきます。
そして現経営者が退陣するまでの役職・持株割合・関係各所に対する通知の方法なども記しておくと、いざというときに戸惑うことがありません。
後継者教育の進め方・持株割合・その後の役職なども記載しますが、現在から10年後までなど一定期間分を記載しておく必要があります。
事業承継計画書のテンプレートを活用する
事業承継計画書には他にも記載しなければならない数多くの項目があるため、作成するときには何を書けばよいのか迷うこともあるでしょうし、手間もかかります。
必要な項目を網羅できていなければ意味がないため、スムーズに作成するためにも事業承継計画書のテンプレートなど活用するとよいでしょう。
たとえば中小企業庁の公式サイトでは、「事業承継ガイドライン」として事業承継を進める上での様々な悩みに答えています。
チェックシートや事業承継計画の作成方法なども掲載されているため、参考にすることをオススメします。
まとめ
事業承継が進まない中小企業数が今後さらに増えてしまうと、廃業や倒産する企業数を増加させることになり、特に地方での雇用を減少させることになります。
中小企業の事業承継問題は日本経済全体の大きな課題としてとらえ、スムーズに進めていける体制を整備していくことが必要です。
これまで築き上げた会社の信用や実績などを無駄にしないように、そして会社に貢献してくれている従業員を路頭に迷わせないためにも、事業承継の準備をしておくようにしましょう。
事業承継の方法はいくつかありますが、いずれにしても事前準備なしでは進みませんし、前もって決めておかなければならないことがたくさんあります。
いざというときに慌てないように、結局事業承継できず廃業してしまわないためにも、早めの対策をオススメします。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。