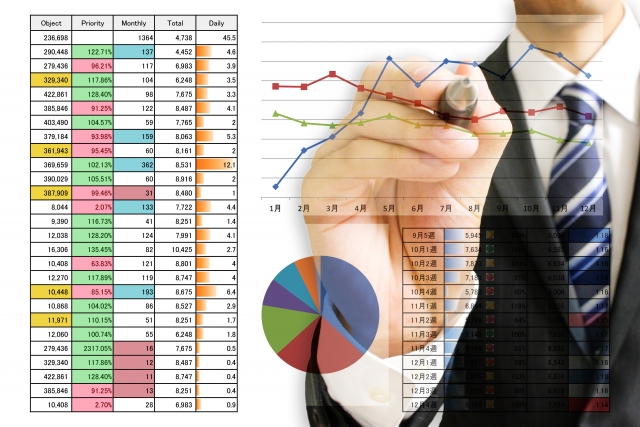今の経営状態を把握し、分析したいときには損益計算書をうまく活用するべきです。
損益計算書とは決算書の1つであり会社の経営成績を示すものといえますが、分析によりどのようなことを確認できるのか、その内容を解説していきます。
目次
損益計算書があらわす内容とは
損益計算書とは、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書と同じく決算書を構成するものの1つであり、1年間で会社がどのくらい儲け損をしたのかその経営成績を示すものです。
売上高などの収益と、それに対し必要とされた仕入れや経費、そして利益や損失がどのくらいになったか損益計算書を見れば把握できます。
5つの利益に分けて表示される理由
損益計算書では、収益と費用が段階的に表示されます。
計上された売上高から支払った費用などを順番に引き、最終的にプラスになれば黒字、マイナスになれば赤字をあらわします。
そして活動ごとに、
- ・売上総利益
- ・営業利益
- ・経常利益
- ・税引前当期純利益
- ・当期純利益
という5つの段階に分け利益が表示されます。
会社の利益は収益から費用や損失を差し引けば計算できますが、それではどのような活動でどのくらいの損益が発生したのかまではわかりません。
経営状況を把握し分析するためには、収益・費用・損失がどのように発生したのか把握することが必要です。
そこで、たとえば仕入れなど売上高に直接対応する部分を差し引いた粗利益を把握し、本業に関わる広告宣伝費や人件費などの費用を差し引いた利益はどのくらいか確認できるように5つに分け表示されます。
損益計算書を分析するときの利益

損益計算書は5つの段階で利益が表示されますが、それぞれどのような内容を示すのか、経営状況を分析する上で知っておくようにしましょう。
売上総利益
売上高から売上に直接対応する仕入れや売上原価を差し引いた粗利益が売上総利益です。
売上総利益=売上高-売上原価
で算出できます。
売上原価は、たとえば卸売業なら商品の仕入れ原価、製造業なら販売した製品の製造原価のことです。
売上高のうち売上総利益の占める割合が売上総利益率で、
売上高総利益率(%)=売上総利益(粗利)÷売上高×100
で算出します。
業種別の平均値の目安は、
製造業 22.3%
卸売業 11.8%
小売業 27.6%
建設業 17.7%
飲食業 56.8%
となっています。
適正な売上総利益率は業種ごとに異なるといえますが、サービス業では高め、小売業では低めになることが一般的です。
営業利益
本業で稼いだ利益を示すのが営業利益であり、
営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費
で算出できます。
販売費及び一般管理費とは、売上原価に含まれない通常の業務にかかる費用のことです。
そして企業が保有する本来の実力は売上高営業利益率を見ればわかります。
売上高営業利益率の計算式は、
売上高営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
です。
多くの業界で1~5%あればよいとされています。
経常利益
会社の企業活動による総合的な収益力をあらわすのが経常利益であり、本業以外の企業活動も含めた収益力といえます。
経常利益は、
経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
で算出できます。
営業外収益として挙げられるものは、たとえばお金を貸したときや預金により発生した金利です。
反対に借入金の利息は営業外費用に含まれますので、借入が多く支払利息を多く負担することとなれば、経常利益は減少するということです。
そして企業の基礎体力を示す指標が経常利益率です。
経常利益率は、
経常利益率(%)=経常利益÷売上高×100
で計算できます。
一般的には4%が平均値ですが、10%前後を目指しましょう。
税引前当期純利益
税金を差し引く前の利益や損失までの利益が税引前当期純利益であり、
税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失
で計算できます。
特別利益や特別損失には、通常の企業活動で発生しない臨時的な利益や損失を含みます。
たとえば特別利益として挙げられるのは、所有する土地を売ったときの利益などで、特別損失となるのは自然災害による損失などです。
当期純利益
税引前当期純利益から法人税など税金を差し引いた後の利益が当期純利益で、
当期純利益=税引前当期純利益-法人税等
という式で算出します。
企業活動では法人税だけでなく、住民税・事業税・固定資産税などいろいろな税金を納めることになります。
会計上はいずれも費用として扱う税金ですが、税引前当期純利益の下に記載される税金とされるのは、法人税・住民税・事業税の所得割だけです。これらの税金以外は、租税公課として販売管理費に計上し処理しています。
会社の最終的な利益であり、プラスであることが当然望ましいといえます。
当期純損失の状態が長期化すれば、経営状況は悪化するため黒字経営を目指すことが必要です。
その他確認しておきたい指標
他にも経営状況を分析する上で確認しておきたい指標はあります。
たとえば自己資本利益率は、自己資本に対する当期純利益を示しており、
自己資本利益率(%)=当期純利益÷自己資本×100
で計算できます。
自己資本は負債を除いた資本ですが、
自己資本=純資産-新株予約権-少数株主持分
で算出してください。
また、総資本利益率(ROA)では総資産に対し生み出した利益を確認できます。
資本を効率的に運用できているか示す指標であり、
総資本利益率(%)=当期純利益÷総資本×100
で算出可能です。
総資本は自己資本に負債による資本も合わせたものであり、融資を受けた分も含めたすべての資本をあらわします。
利益率を参考に分析するときの注意
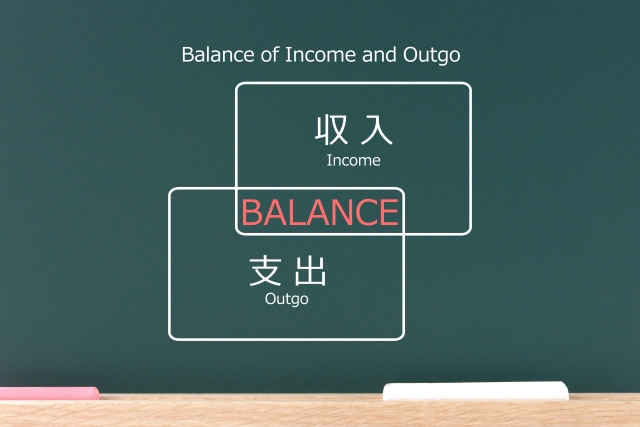
いずれも利益率を経営分析の目安とするときには、同じ程度の規模の同業他社を参考にするようにしましょう。
同じ業種だとしても、大企業と中小企業では数値は変わりますし、何を販売するかによっても変動するからです。
そして会社が獲得した売上高からいろいろな費用を差し引き、本業以外で発生した収益や税金なども調整し、結果として黒字と赤字どちらになったのかを示すもの損益計算書です。
経営分析する上で欠かせないツールといえますが、その際のポイントとして次のことを理解しておく必要があります。
損益とお金の動きは同じではない
損益計算書に計上されている収益や費用は、実際の収入と支出のルールと同じではありません。
収益は実現主義、費用は発生主義が原則であり、収益は実現した時点、費用は確定した時点で計上します。
手元のお金の出入りとは同じ動きではないため、損益計算書だけにとらわれれば実際の資金繰りを見失うことになっていまいます。
順調に売上が伸び収益が向上していると安心していると、実際には売上代金の回収ができておらず売掛金ばかりが増え、黒字なのに資金ショートし倒産する事態を招きます。
損益計算書と実際の資金繰りは同じではないことを認識した上での経営分析が必要です。
最も重要なのは経常利益
経常利益は会社の実力を利益で示したものと言い換えることができますが、借入にかかる費用まで考慮した上での利益です。
資金繰り悪化で資金を調達しなければならなくなり、たとえ金利が高くてもお金を借りて準備しなければ!と高額の利息を支払っていれば経常利益は低くなってしまいます。
しかし営業利益が低くても、資金の運用がうまくできていれば経常利益が高くなることもあるのです。
会社存続に必要なことは、営業活動だけでなく総合的な力の維持であり、経常利益は会社の実力を判断する上で確認しておきたい利益といえます。
まとめ
損益計算書を使った会社分析において、5つに分類される利益の意味やルールなどを把握しておくようにしましょう。
また、損益計算書の損益と実際の手元のお金の動きは同じではありません。たとえ利益が出ていても手元の資金がショートすれば倒産リスクを高めることを十分理解した上で、会社の経営分析を行っていくようにしてください。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。