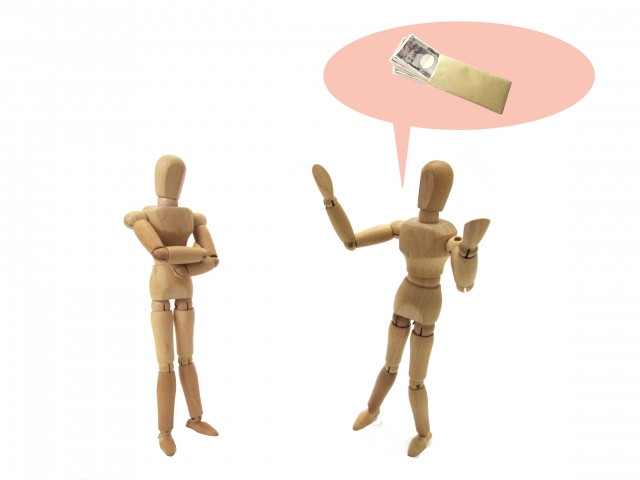メディアなどで、情報の隠ぺいや文書の改ざんなどの問題が取りあげられることもありますが、このような行為で不法な取引を行うと、詐欺罪で実刑という判決が下ることもあります。
資金を調達するために、ファクタリングを利用する中小企業や個人事業主も増えていますが、ファクタリングにおいても同様です。
そこで、ファクタリングの場面において行われる不法行為や詐欺行為とはどのようなケースなのか、その内容をご説明します。
目次
ファクタリングで利用できるのは実在する売掛債権のみ
企業経営とは、単に利益をあげればよいのではなく、事業活動を通じて社会に貢献することも必要です。そのためには、様々なタイミングで発生することのある資金不足という問題をクリアしていかなければなりませんが、不足した資金を調達するためにファクタリングを検討する場合もあるでしょう。
ファクタリングとは、企業などが保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却して、早く現金化させることにより資金を調達する方法です。
ここで重要になるのは、ファクタリング会社に買い取ってもらえるように持ち込むことができる売掛金は、実在するものであり架空債権ではないものであるということです。
架空の売掛債権が持ち込まれやすいのは2社間での取引
ファクタリングには、2社間と3社間という種類があり、そのうち2社間ファクタリングは利用会社とファクタリング会社のみで取引を行います。3社間とは異なり、2社間では売掛先企業に売掛金が譲渡される事実が通知・確認されることはありません。
そのため利用会社の中には、架空の請求書などを作成・偽造し、偽の売掛金をファクタリング会社に持ち込んで資金化しようとするケースもみられます。
しかし、架空の請求書を作成・偽造する行為は、詐欺であり、犯罪です。私文書偽造という罪にとわれることとなり、懲役刑や実刑、というケースもありますので絶対に行わないことが大切です。
ファクタリングで詐欺罪とされた事例

どのような流れでファクタリングにおいて詐欺罪とされるのか、過去にファクタリング取引で詐欺の罪にとわれることになった例をご紹介します。
資金に困ったX社の事例
ファクタリングを資金の調達方法に用いることを決めたX社では、ファクタリング会社に持ち込むため、すでに取引が終了している売掛先といまだに継続して取引が行われているように見せかけるための嘘の請求書を作成します。
預金通帳の写しの数字も偽造し、毎月、取引が終わっている売掛先から売掛債権分が入金されていることにして、ファクタリング会社と契約を結び資金を調達しました。
その後、売掛先から売掛代金が支払われるはずの期日を迎えても、X社から売掛代金の入金はされませんでした。当然ですが、売掛先とX社の間で取引は発生していませんので、入金される売掛代金そのものが存在していません。
もしかしたらX社は、売掛先から入金されると設定した偽の期日までに、何らかの方法で資金を準備し、ファクタリング会社に支払う予定だったのかもしれません。
しかし決済期日を迎えてもX社から入金はされなかったため、ファクタリング会社からX社に連絡を入れても、後日支払うと伝えられます。しかし、X社が支払うと言った日になってもやはり入金はされなかったため、ファクタリング会社は売掛先に債権譲渡通知書を送り、債権の回収を試みます。
しかし、売掛先からはX社とは取引を行っておらず、支払う債務はないとの回答でした。しかもこのX社は、他のファクタリング会社にも同様の手口で売掛先に対する架空の売掛債権を作り、1,000万円近くの資金を騙し取っていたようです。
その結果、ファクタリング会社同士が協力し、X社の代表を刑事告訴することとなり、この経営者は詐欺罪と私文書偽造罪、同行使罪などに問われることなり、懲役3年10か月の実刑判決を受ける流れとなったとされています。
詐欺罪の構成要件を満たせば詐欺罪が成立
ファクタリング会社を騙し、錯誤に陥らせて資金を拠出させ、損害を与えれば罪に問われます。詐欺罪の構成要件を満たせば詐欺罪が成立すると認識しておくべきでしょう。
詐欺の被害金額が500万円を超えた場合、刑事告訴されれば執行猶予は付かずに実刑となるケースもあるため、このような不法な取引は行わないようにするべきです。
架空の売掛債権を資金化する行為は犯罪

ファクタリングは、売掛債権の売買により、売掛金の買い手から売り手に資金が流れる仕組みになっています。
しかし、当然、存在しない売掛債権は売ることはできません。存在しないものを存在するかのように見せかけて取引に持ち込み、金銭を得る行為は詐欺以外何ものでもないのです。
請求書や契約書の偽造、預金通帳の入金履歴の偽造、取引履歴のねつ造など、このような偽装工作を駆使してつくった架空債権を現金化することは立派な犯罪です。
悪気がなかった…というケースでも罪は罪
実際、このような詐欺行為で資金を調達しようとする方の中には、ファクタリング会社を陥れようと考えていないケースもあります。
たとえば銀行融資や政府系金融機関からの借入審査などの場面で、自己資金があるように見せかけるために、一時的に家族や友人などからすぐに返すという約束でお金を借り、口座に入金して預金があるように見せかけ、融資を受けようとするケースもゼロではありません。しかしこの行為も、拡大解釈すれば債権偽造という罪に問われる可能性だって否定できないでしょう。
ファクタリングを利用しようとする方の多くは、急いで資金を調達し、現在の危機を乗り越えたいと考えているケースです。何とかピンチを乗り切りたいという思いで、偽の請求書作成という行為に及ぶこととなり、結果、詐欺罪という罪に問われることになってしまうのかもしれませんが、罪は罪だと理解しておくべきです。
不法行為と刑罰の違い
法律上、損害を与える行為は罰せられることになります。詐欺を行った場合、民事上の不法行為、刑事上の犯罪という2つの行為が存在しますが、刑事上の詐欺なら民事上の不法行為にもなります。
民事上の不法行為とは、故意または過失による違法行為で、他人の権利や利益を侵害した場合、発生した損害を賠償させるための民法上制度を指します。
刑事上の犯罪とは、社会生活を送る上での利益を侵害する有害な行為であり、刑罰による制裁が必要であるものです。
金銭などで解決できれば民事事件
事件が発生した場合、当事者同士で直接、金銭などで問題解決に至ることができるものは民事事件として扱われることとなり、被害者からは加害者に対して損害賠償請求を行うという形になります。
国が刑罰を科すのか決めるのが刑事事件
国が刑罰を科すかどうか決定づけるのが刑事事件であり、そこにはその行為が犯罪に該当するのかが問題となります。警察が介入し、加害者を逮捕や勾留し、刑務所で懲役刑を受けることになるのかとう部分です。
刑罰として扱われる場合にも、罰金という制度があることでその行為が犯罪か不法行為なのかわかりにくくしているともいえるでしょう。
ただ罰金はあくまでも被害者が受け取るものではなく、刑罰として国に支払うものであるため、民事で発生する損害賠償請求とはまた違った扱いです。混同しないようにしておきましょう。
まとめ
ファクタリングで資金を調達しようとするとき、ファクタリング会社に持ち込む請求書が偽物だったとしたら、その行為は詐欺に該当します。
不法行為として、ファクタリング会社にお金を返金すれば解決する問題では終わらず、刑事事件として扱われることになれば、罰金以外に懲役や実刑という可能性も出てくるでしょう。
実名が報道されることになれば、社会的な信用を失うこととなり、事業を継続させるつもりで行った行為なのに、結果、事業を終わらせなければならなくなります。
資金に苦しみ、つい架空の売掛債権を作ってしまったというケースや、預金口座の数字を偽造してしまったというケースもありますが、これらはファクタリング会社を騙そうとする行為ですので絶対に行わないようにしてください。
事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
事業支援Labは中小企業の経営者を総合的にサポートします。
- 事業を安定させたい方
- 新規事業を立ち上げたい方
- 経営に関する相談をしたい方
- 資金繰りにお困りの方
- 保険として資金調達先を知っておきたい方
コロナウィルスの影響や世界情勢の不安、急激な円安進行..
大きく環境が変化する中で、なかなか経営が安定しなかったり、新規事業の立ち上げに苦慮する企業が多くなっています。
事業支援Labは日本を支える中小企業の経営者を総合的にサポートし、多種多様な専門家を無料でご紹介しています。
事業計画から資金繰りまで経営に関する問題解決に取り組むパートナーとして、経営者の皆様のビジョンの実現を支援いたします。
まずはお気軽にご相談ください。